高額療養費制度
高額療養費
国民健康保険に加入している方が保険診療を受け、同じ月内に支払った医療費が次の区分による自己負担限度額を超えたときは、申請により、その超えた分が高額療養費として国民健康保険から支給されます。
70歳未満の方
70歳未満の方は、医療機関、診療科ごとでそれぞれ合計します。(総合病院の外来において複数の診療科を受診した場合、その病院での診療は合算することとなります。ただし、歯科は別に計算します。)
同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上自己負担した場合は、それらを合算することができます。
| 区分 (旧ただし書き所得) |
自己負担限度額 | 自己負担額 (4回目以降(※1)) |
| 901万円超 | 252,600円+(総医療費(※2)-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 600万円超 901万円以下 |
167,400+(総医療費(※2)-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費(※2)-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 一般 | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
(※1) 過去12か月以内に、同一世帯で4回以上高額療養費に該当した場合は「4回目以降」の自己負担限度額が適用されます。
(※2)支払った金額ではなく、医療費の総額(10割分)となります。
70歳以上の方
70歳以上の方は、医療機関や診療科ごとに区別せず、支払った医療費を合算することができます。
| 区分 | 外来のみ(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費(※1)-842,000円)×1% |
|
| 現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費(※1)-558,000円)×1% |
|
| 現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費(※1)-267,000円)×1% |
|
| 一般(課税所得145万円未満等) |
18,000円 |
57,600円 |
| 低所得II | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得I | 8,000円 | 15,000円 |
(※1) 支払った金額ではなく、医療費の総額(10割分)となります。
(※2)過去12か月以内に、同一世帯で4回以上高額療養費に該当した場合は「4回目以降」の自己負担限度額が適用されます。
- 「現役並み所得者」とは、住民税の課税所得が145万円以上の方とその同一世帯の方。「低所得II」とは、住民税非課税世帯の方。「低所得I」とは、住民税非課税世帯で、全員の所得が0円の世帯の方。
- 月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、自己負担限度額は本来額の2分の1になります。(毎月1日生まれの方は対象外)
- 住民税の申告をされていない世帯は、高額療養費の支給ができません。
高額療養費の申請について
高額療養費の該当となる方で、申請手続きの簡素化を行っていない方については、診療を受けた月の2~3か月後に対象者に申請書をお送りいたします。
申請時には病院への支払いが済んでいることを確認させていただきますので領収書は捨てずに保管してください。
申請時に必要な持ち物
- 該当月の領収書
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 認印
- 振込先口座の控え
- 世帯員全員のマイナンバーカード(ある方のみ)
- 来庁者の本人確認できる物
高額療養費申請手続きの簡素化について
令和3年10月から、初回の申請に合わせて簡素化の手続きをすることで、それ以降に該当になった高額療養費については、月ごとの申請手続きをせず、高額療養費が指定の口座へ振り込まれます。
※ 国民健康保険税の滞納がある世帯については手続きを開始できませんので納期までの支払いをお願いします。
簡素化の申請について
対象世帯には、療養月の2~3か月後に高額療養費申請書と併せて申請手続簡素化該当世帯用の申請用紙を郵送します。
希望する場合には手続きをしてください。
申請手続簡素化が停止する場合
次の場合には申請手続簡素化を停止します。
・国民健康保険税の滞納がある場合
限度額認定証
マイナ保険証をお持ちでない方で、高額な医療にかかる方について、事前に交付申請をしていただき、資格確認書と一緒に限度額適用認定証を保険医療機関に提示することで、各医療機関窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。
なお、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証により限度額の適用を受けることができるため、発行できません。
交付申請について
70歳未満の方
申請により限度額適用認定証を発行することができます。
70歳以上の方
現役並み所得者I、IIの方と低所得I、IIの方は申請により限度額適用認定証を発行することができます。
現役並み所得者IIIの方と一般の方は、資格確認書を提示することで自己負担限度額までとなりますので、申請は不要です。
- 国民健康保険税の滞納がある場合は交付することができません。
- 住民税の申告をされていない世帯は、上位所得者扱いとなります。
- 対象となる医療機関
- 保険医療機関
- 保険薬局
- 指定訪問看護事業者
限度額・標準負担額減額認定申請書 (Wordファイル: 24.4KB)
食事療養費
入院をした場合、食事代に関しては1食510円が自己負担、残りは食事療養費として国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯の方はマイナ保険証の利用又は、限度額適用認定証の提示により下記の負担額になります。
なお、90日を超える入院の場合、マイナ保険証を利用して入院する場合でも申請が必要となりますのでご注意ください。
減額していない額の食事代を病院へ支払った場合に、減額できなかったことがやむを得ないものと判断した場合のみ、申請により差額を支給いたします。
| 一般(下記以外の人) |
510円 ※ |
|
| 住民税非課税及び低所得II |
(90日までの入院) |
240円 |
| (過去12か月で90日を超える入院) |
190円 |
|
| 低所得I |
110円 |
|
※ 一部300円の場合があります。
特定疾病療養受給証
長期間にわたって高額な治療を必要とする下記の疾病の方は、所定の手続きをし「特定疾病療養受療証」の交付を受けると、自己負担限度額が医療機関ごと、入院・外来ごとに10,000円(月額)となります。
対象となる疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
※人工透析を要している70歳未満の上位所得者(基礎控除後の年間所得金額が600万円を超える世帯の方)は、自己負担限度額が20,000円(月額)となります。
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8又は第9因子障害(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請(相談)窓口
- 小諸市国民健康保険又は後期高齢者医療制度の方
⇒ 市民課・国保年金係 電話 0267-22-1700(内線2120、2122、2123) - 全国健康保険協会(協会けんぽ)の方
⇒ 全国健康保険協会の各都道府県支部(長野支部 電話 026-238-1250) - その他保険(共済組合・建設国保など)の方
⇒ ご加入の保険の事務局へお問い合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課 国保年金係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
お問い合わせはこちらから
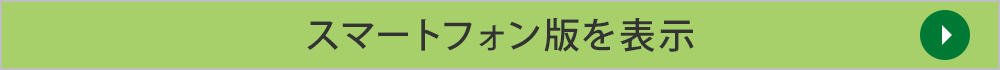
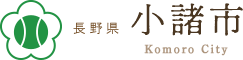
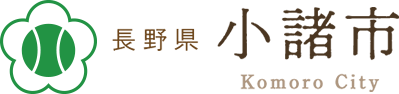

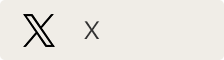


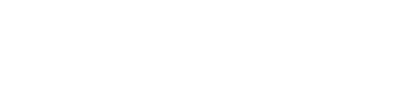

更新日:2025年07月30日