施政方針
令 和 7 年 度
施 政 方 針
小諸市長 小 泉 俊 博
本日、令和7年3月小諸市議会定例会の開会にあたり、私の市政経営に対する所信の一端を申し述べ、市議会並びに市民の皆様の 一層のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
私は、昨年4月の市長選挙におきまして、大変多くの皆様のご支持をいただき、三度、小諸市政の舵取りの重責を担わせていただくこととなりました。
そして、この一年も、市民の皆様の期待にお応えするという強い使命感と責任から身の引き締まる思いで、鋭意、市政経営に取り組んでまいりました。
私は、3期目の公約の中で、小諸市が今後も持続可能な自治体であり続けるためには、人口減少を抑制しつつ、市内外の人々から「選ばれるまち」であることが必要であり、そのために2期目に引き続き、「小諸版ウエルネスシティ~第2章~」として、「あらゆる分野で健康・健全で自己実現できるまち、自分に還る・何度でも帰りたいまち、住みたい・住み続けたいまち」を小諸市のあり方・ビジョンとして掲げ、まちづくりの施策を展開していくこととしました。
「小諸版ウエルネスシティ」は、人口が減少する時代にあっても人に選ばれる、ここに住んでよかったと思えるまちになるため、これからの小諸市のあるべき姿を示したもので 、小諸市独自の概念になります。そして、ここに住む人々が健康で生きがいをもって安全・安心で豊かな人生を営めるまち、最後まで自分らしく人生を全うできる地域社会を目指すものです。
また、慌ただしい高度情報化社会、ストレス社会に生きる現代人には、快適で心地よい場所、自分に還れる場所、ウエルネス資源により自己開発、自己実現できる場所などが必要となりますので、そうした場所として「ウエルネス・サード・プレイス」を目指すことを大きな特徴としています。
このことは、小諸市の総合計画の根幹となる第5次基本構想の将来都市像「住みたい 行きたい 帰ってきたい まち小諸」とも整合性があります。この観点を踏まえた第12次基本計画の政策分野別の内容につきましては、後ほどご説明させていただきます。
さて、令和6年度を振り返りますと、一昨年の5月に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に変更になったことに伴い、市民生活がコロナ禍以前の生活に戻りつつあり、人と人との交流も再開され、市内における各種イベント等も通常開催されるなど、賑わいが戻ってきた一年でありました。
しかし、昨年の元日には能登半島地震が、9月には同じ能登地域で記録的な大雨災害が発生し、さらには日本をはじめ世界各地で危険な暑さや異常気象も続くなど、激甚化・頻発化している自然災害に対して、今後も一層の備えが必要であると改めて強く認識する年でもありました。また他方では、ロシアによるウクライナ侵攻に加え、中東情勢の緊迫化や円安の進行などにより、原油価格をはじめ食品などの物価高騰が、市民生活に多大な影響を及ぼした一年となりました。
そのような状況下ではありましたが、小諸市は市制施行70周年を迎え、昨年11月には、市民の皆さまをはじめ、関係の皆さま、また、多くのご来賓の皆さまにご臨席を賜り、記念式典を挙行することができました。式典では、オープニングとして、美南ガ丘小学校合唱部の皆さんと辛島美登里さんとのコラボレーションによる歌の披露から始まり、小諸高校音楽科の生徒による国歌独唱や、芦原中学校、小諸東中学校両校の生徒会長による市民憲章の朗読、小学生と高校生による未来(あす)の小諸へのメッセージなど、次の世代を担う皆さんにも登壇いただき、ふるさと小諸に対する熱い思いを語っていただきました。式典の最後には、野岸小学校管楽部の皆さんによる演奏が披露され、厳粛な中にも和やかで心温まる雰囲気の中、滞りなく式典を挙行することができました。市制施行70周年という節目の年、これを新たな契機とするとともに、先人の方々の足跡をしっかりと踏まえ、改めて、市民の皆様とともに、持続可能なまちを目指し、取り組んでまいりたいと気持ちを新たにしたところであります。
その節目となる令和6年度に進めてきた事業の中で特徴的なものにつきまして、ご説明申し上げます。
子育て・教育の分野では、家庭における子育ての負担や不安、孤立感を和らげ、安心して子育てができる環境づくりを、行政と家庭や地域が連携し、社会全体で取り組む体制づくりを目指し、子どもと子育て家庭の総合窓口として「こども家庭センター」を設置しました。特に、保育園においては、未満児保育ニーズに対応できるよう保育人材の確保に努めるとともに、保育環境の充実を図っているところです。また、こもろ未来プロジェクト2024教育編として、小諸市の教育の目指すべき姿や方針を定めた「第3期小諸市教育大綱」を策定しました。この中において、仲間と共に協働的に学び合う学びの実現をはじめとした「小諸市が目指す教育」を推進するため、小諸市全体で小中一貫教育を推進し、義務教育学校の設置を目指すことも明記いたしました。
文化財、生涯学習については、小諸の歴史的、文化的なお宝や自然の素晴らしさなどを楽しみながら体験する「ふるさと学習」を市内小中学生対象に積極的に推進し、ふるさとを愛し大切に思う郷土愛溢れた子どもの育成に努めてきました。
旧小諸本陣の修理復原工事では、着実に工事を進めており、現在、観光面とのつながりを深める施策の検討を行っているところです。
スポーツについては、2028年に長野県で開催される第82回国民スポーツ大会で、小諸を舞台としてレスリング競技が行われることから、新設した国民スポーツ大会準備室を中心に関係団体と連携を図るとともに、第82回国民スポーツ大会小諸市準備委員会の設立総会・第1回総会を開催し、早期の大会準備に取り組む体制づくりを進めました。
人権関係については、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、または軽減し、再び平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、昨年4月に小諸市犯罪被害者等支援条例を制定しました。また、働く女性が地元で自分らしく職業生活が送れるよう、私自らが「女性から選ばれる長野県を目指すリーダーの会」の幹事になり、男女共同参画に係る取組に積極的に関わることといたしました。
次に環境の分野では、「脱炭素先行地域づくり事業」に関するキックオフシンポジウムを開催し、市民、事業者、行政等が一丸となって地球温暖化防止、ゼロカーボンの実現に向け取り組むことで、持続可能な社会の実現を目指す決意を内外に示しました。これに伴い市としまして、市庁舎等への太陽光発電設備や公用車のEV化、EV充電設備の整備等に着手するとともに、子どもを対象とした環境教育等を実施してまいりました。また、小諸市動植物の保護に関する条例により「オヒョウ」を保護動植物に追加指定するなど、環境保全にも力を入れてまいりました。
次に健康・福祉の分野では、デジタルを活用した新たな子育て支援策として、従来の紙による母子健康手帳をデジタルデータとして記録できる母子手帳アプリ「母子モ」を導入し、時代に即し、きめ細やかな子育て支援を実施しました。また、介護人材の不足が叫ばれる状況下において、専門資格がなくてもできるお手伝いをしていただける方の有償ボランティア「スケッター」を開始し、介護人材の確保を図りました。昨年4月には小諸市手話言語条例が施行され、手話に関する理解の促進、手話の普及及び手話の使いやすい環境の整備を図りました。
次に産業・交流の分野では、令和6年度の単年度において、中心市街地で新たに20店舗が営業を開始するなど、賑わいが生まれています。小諸市動物園では、開園100周年に向け、国のデジタル田園都市国家構想交付金(地方創生拠点整備タイプ)を活用し、小諸市動物園第二期エリア整備工事を実施しました。
農業振興では、世界的ワイングラスメーカーであるRSN Japan株式会社(リーデルジャパン)と連携協定を締結しました。これは小諸市が高品質ワインの代表的な産地であると認められたものであり、「小諸ワイン」のブランド化やワイン産業等による地域活性化に向けた取組がさらに進むことになります。森林整備では、市内で実施する自伐型林業による地域課題解決の取組が全国的に評価され、一般社団法人プラチナ構想ネットワークが主催する、第12回プラチナ大賞の優秀賞を受賞しました。
次に生活基盤整備の分野では、旧小諸本陣・大手門・三之門地区文化・観光交流拠点化プロジェクトの一環としてUR都市機構が旧竹内木材の土地・建物を取得して、民間事業者による活用を行う公民共創の事業が始まりました。
上水道事業においては、小諸市水道事業給水開始100周年を記念し、式典を開催するとともに、今後の持続可能な取組として、上下水道一体での官民連携(ウォーターPPP)の導入に向けた調査・検討を始めました。
我が国最初の火山観測所が浅間山(湯の平)に設置され、観測を開始した明治44年8月26日にちなみ、国が8月26日を「火山防災の日」に制定したことを受け、その浅間山火山観測所跡を市の史跡に指定しました。また、自然災害が多発する中で、令和6年度長野県総合防災訓練が小諸市を会場に16年ぶりに開催され、ドローン物資輸送訓練やキッチンカーによる炊き出し訓練など、能登半島地震の教訓を活かした訓練を取り入れて実施されるとともに、関係機関、関係団体、多くの市民の参加により、防災に関する意識の向上が図られました。
最後に協働・行政経営の分野では、行政マネジメントの最上位計画である「小諸市総合計画第12次基本計画」に、市長マニフェストを反映させるとともに、第11次基本計画に引き続き、SDGsの推進を取り入れて策定しました。また、人口減少を克服し、自律的で持続的な社会の創成を目指す「小諸市第3期まち・ひと・しごと総合戦略」は、第12次基本計画を補完する計画と位置付け、本年3月末の策定に向け作業を進めています。
また、貴重な自主財源であり、地域経済の振興にも繋がる「ふるさと納税」につきましては、魅力ある返礼品の掘り起こしや新規開発等の創意工夫により、自主財源の確保に努めているところです。
これまでの間、さまざまな政策・施策が実を結び、令和2年から5年連続での人口の社会増を記録することができました。これは、基本計画に基づく6つの政策、それに紐づく施策の実施のみならず、関係する機関や団体、それぞれ活動されている市民の皆さまをはじめとするオール小諸市としての取り組みにより、小諸市が「選ばれるまち」になってきていることが証明された実績であると考えています。この流れを止めることなく、令和7年度についても、引き続き事業を展開してまいりたいと思います。
さて、令和7年度は、これまでに築いた土台(方向・方針)を基に、着実に歩みを進めていくという意味で、大変重要な年であると考えております。小諸市には、人口減少対策や公共施設の計画的な更新、未利用公共施設の利活用など、まだまだ課題が山積しておりますが、引き続き、小諸の未来のために、誠実に、粘り強く、全力を尽くしてまいります。
それでは、令和7年度の重点施策につきまして、「第5次基本構想・第12次基本計画」の政策分野別にご説明申し上げます。
なお、事業の詳細につきましては、今議会におきまして、「予算(案)及び実施計画の説明」の際にご説明いたします。
1 心豊かで自立できる人が育つまち「子育て・教育」
まず、一つ目は、心豊かで自立した人が育つまち「子育て・教育」の分野です。
昨年12月に、こもろ未来プロジェクト2024教育編として策定しました「第3期小諸市教育大綱」を羅針盤とし、子どもたちが心豊かに、自ら考え行動できる人として育ち、全ての市民が生涯にわたって学び続ける社会の実現に向けて、教育委員会と共に、施策の推進を図ってまいります。
学校再編については、令和10年度の芦原中学校区の統合小学校(義務教育学校)の開校を目指し、学校建設の基本設計、実施設計を進めるとともに、学校運営の検討等の取組を着実に進めてまいります。
また、こどもたち一人ひとりに新たな時代を生き抜くために 必要となる資質・能力が育つよう、小諸市全体で小中一貫教育を 推進し、小諸市の教育が目指す「心豊かで自立したこども」を育成するための学校づくりに取り組んでまいります。引き続き、市民をはじめ移住者の皆様にとっても、より魅力的な教育環境づくりに 努めてまいります。
小諸市の誇る安全で美味しい「自校給食」の安定的な提供に、 引き続き取り組んでまいります。
休日の学校部活動の地域クラブ活動への移行に向けた実証事業に取り組み、小諸市の実情に応じた持続可能な体制づくりを確立してまいります。
「こどもまんなか社会」の実現に向け、昨年設置しました「こども家庭センター」において、家庭における子育ての負担や不安、孤立感を和らげ、安心して子育てができる環境づくりを、行政と家庭や地域が連携し、社会全体で取り組む体制づくりを確立してまいります。また、未満児保育ニーズに対応できるよう保育人材の確保に努めるとともに、保育士業務の効率化など保育環境の充実を図ってまいります。特に、保育士の確保については、昨年度に引き続き、正規職員の計画的な増員採用を図るとともに、将来にわたりより良い保育環境が提供できるよう、保育園の再配置計画の策定を進めてまいります。
文化財、生涯学習については、市民の主体的な「学び」を促進するため、ニーズを捉えた学習機会の創出や、快適に利用できる施設環境の整備に取り組みます。「音楽のまち・こもろ」では、引き続き小中学校の音楽活動を推奨するとともに、これまで実施してきた事業の創意工夫と充実により市民の音楽文化のさらなる発展を図ってまいります。生涯学習施設については、長寿命化と複合化、多機能化など、計画的な施設整備と市民や利用団体の皆様が快適に利用できるよう環境整備に取り組みます。
旧小諸本陣問屋場の復原工事では着実に工事を進めるとともに、観光面とのつながりを深めるなど、積極的な有効活用についての検討を進めてまいります。また、小諸城址懐古園の名勝指定は、国指定を目指し準備を進めてまいります。旧北国街道沿いの小諸宿の歴史的町並み形成については、保存だけでなく、積極的な活用により、まちづくりにつなげることを基本とし、地元地区や関係団体と連携協力しながら地域の合意形成など、丁寧に進めてまいります。
スポーツについては、多様なスポーツニーズに応じた機会の充実により、市民のスポーツ振興を図ってまいります。特に子どもたちにとっての運動は、生涯スポーツの基礎となり、育ちの一助となります。高地トレーニングで小諸を訪れるアスリートや競技団体と、子どもたち、市民が交流する事業など様々な機会を積極的につくり、スポーツを身近に感じる取組を進めてまいります。
また、2028年に長野県で開催される第82回国民スポーツ大会では、小諸を舞台としたレスリング競技の成功に向けて、新設した国民スポーツ大会準備室を中心に長野県や長野県レスリング協会など、関係団体と連携を密にしながら着実に準備を進め、併せて、気運を醸成し、市民のスポーツへの関心を高めてまいります。
人権関係については、すべての家庭・職場・地域における社会人権同和教育や学校人権同和教育、各種研修会、啓発活動を計画的かつ積極的に推進し、子ども、女性、外国人、性の多様性、同和問題、インターネット上の人権侵害など、あらゆる人権問題に対する正しい理解と認識を高め、市民の人権尊重意識の高揚を図ります。また、男女共同参画及びジェンダー平等社会の実現を目指します。
2 自然環境を守り、循環型社会の進んだまち「環境」
二つ目は、自然環境を守り、循環型社会の進んだまち「環境」の分野です。
小諸市の豊かな自然環境は、先人たちが日々の暮らしの中で、深く関わり、守り育ててきたものであり、この貴重な財産を健全な形で未来につなげることが、現代を生きる私たちの使命です。今の暮らし方を見つめ直し、森林・水資源の保全、ごみの減量化・再資源化等を進めることにより、将来にわたり持続可能な循環型社会の形成を図ります。
また、地球温暖化防止に努め、自然環境にやさしいまちづくりを進めます。そのために、市民、事業者、行政が環境に対する意識をさらに高め、それぞれの役割と責任を意識し、省エネルギーの徹底や環境、景観、地域との調和を図りながら、再生可能エネルギーの活用を推進し、温室効果ガスの削減に取り組みます。
そして、市民の自発的、主体的な行動を促進するための助成や、脱炭素先行地域づくり事業を実施してまいります。
さらに、地域との合意が形成され、自然環境と調和した再生可能エネルギーの普及を図るため「太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」を厳格に運用します。
「第3次環境基本計画」及び「第2次ごみ処理基本計画」に基づき、良好な自然環境及び生活環境を維持、保全してまいります。特に、地球温暖化防止、ゼロカーボンの実現へ向け「小諸市ゼロカーボン戦略推進本部」を中心に、基本協定を締結している企業や各種団体の皆様と連携協力しながら、市民への情報提供と啓発を進めます。また、「動植物の保護に関する条例」を適切に運用すること等で、市民意識の高揚を図り、本市の豊かな自然環境の保全を図ります。
下水道事業においては、排水処理施設の整備・共同化計画の見直しにより、将来の施設構成を形作るとともに、「経営戦略」において、第2期「ストックマネジメント計画」を連携することで、より正確性の高い受益者負担のあり方を検討します。
また、上水道課と連携し、上下水道一体での官民連携(ウォー ターPPP)の導入へ向け、将来にわたって持続可能な事業運営を 目指します。
3 一人ひとりが健康に心がけ、みんなで支え合うまち「健康・福祉」
三つ目は、一人ひとりが健康に心がけ、みんなで支え合うまち「健康・福祉」の分野です。
市民の誰もが命を大切にし、命が大切にされるとともに、子どもから高齢者まで全ての市民一人ひとりが健康に心がけ、生きがいを持ち、みんなで支え合いながら活躍できるような地域社会を創ってまいります。
第4次小諸市健康づくり計画「げんき小諸21」に基づき、関係組織や協力団体と連携しながら、食育や健診受診、こもろ健幸マイレージへの参加等、健康に良い生活習慣の定着を推進してまいります。
また、悩みや困難を抱えた時に助けを求めることができ、一人ひとりの命が大切にされるまちを目指し、ゲートキーパーの養成や、がんとの共生事業にも、引き続き力を入れてまいります。
地域医療体制の維持に向けては、医療の適正利用への啓発を行うとともに、小諸市内のみならず、佐久地域における救急医療をはじめとする医療資源に対し、必要な支援を行います。
母子保健事業を通じて全ての妊産婦、乳幼児等へ関わり、必要な家庭にしっかり支援が届くよう「こども家庭センター」において、母子保健と児童福祉の連携を一層強化し、妊娠から出産、子育てまで、切れ目ない支援につないでまいります。
誰もが生きがいを持って自分らしく暮らせるために、「お互いさま」の心で支え合う仕組みがつくれるよう、地域福祉計画・地域福祉活動計画に沿って地域福祉施策を推進するほか、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく福祉サービスの提供や、通所支援等の提供体制の整備を進めてまいります。
生活困窮・子どもの貧困、生活保護等の様々な相談に対し、庁内関係部署及び関係機関が連携と協調による支援を強化するなど、重層的支援体制の整備を進めます。
また、地域福祉の要である民生児童委員の更新年に当たるため、充足率100%となるよう地域と協力し、あわせて、活動支援体制の強化を図ってまいります。
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、引き続き地域包括ケアシステムの構築を推進し、高齢者を支える地域のネットワークの拡充を図ります。
また、高齢者福祉センター「こもれび」を拠点とした介護予防事業を開催するとともに、これまでも力を入れてきた各区の高齢者の通いの場の開催が継続できるよう、引き続き支援してまいります。
要介護認定率が長年にわたり国・県と比較し、低く抑えられている本市の状況を今後も維持できるよう、フレイル(虚弱)の要因である低栄養、口腔機能や運動機能の低下のリスクや生活習慣病がある高齢者を対象に保健指導を充実させることで、疾病の重症化予防、要介護状態となることの予防につなげ、健康寿命の延伸を図ってまいります。
そして、高齢者が自らの経験や知見、趣味などを通じ、生きがい・やりがいを実感しながら社会参加できる仕組みを構築します。
4 地域の宝、地域の資源を有効活用し、活気ある豊かなまち「産業・交流」
四つ目は、地域の宝、地域の資源を有効活用し、活気ある豊かなまち「産業・交流」の分野です。
豊かな暮らしの創出と、持続可能な地域を構築するため、「稼ぐ力をもったまち」を目指した戦略的な産業振興策と移住・定住促進策を展開し、働きやすさと住みよさ、暮らして楽しい、訪れて楽しい、魅力あるまちづくりを進めます。
農業振興では、豊かで良質な食を想起させる質の高い地元農産物のブランド化を推進し、産地としての定着と農家所得向上につなげるほか、生産性向上に向けて農地の利用集積や基盤整備を進め、優良農地の確保、継承を図ります。
また、中山間地域での経営安定に向けた取組を進めるとともに、他に先駆けて取組みをはじめた「農ライフ」については、移住施策と組み合わせて推進し、農地の利用促進と遊休荒廃農地の解消につなげてまいります。
安定的な農業経営に欠かせない優良農地においては、良好な状態で次の担い手に引き継ぐため、ほ場整備エリア内の農業用施設の維持補修を計画的に進めるとともに、大規模な整備や改修が必要な農道や水路等は、防災減災対策を含め補助事業を有効に活用しながら事業を推進します。
ゼロカーボンの取組においても重要な森林整備は、森林環境譲与税や森林づくり県民税などの財源を有効活用し、森林整備実施方針に基づき計画的な整備を進めるほか、野生鳥獣被害対策を安定的に実施してまいります。
商工業振興は、引き続き地域の強みを活かした、積極的な企業誘致に取り組むほか、既存企業・事業者の支援も強化します。さらに、新産業団地整備を着実に進めるとともに、商工会議所との連携を深め、起業・創業への支援を強化することで、市内への投資促進はもとより、経済やまちづくりの担い手の誘致・育成に取り組んでまいります。
また、子育てがしやすい働き方ができるまちを目指し、デジタル人材の育成や産業のデジタル化を関係機関と連携して進めるとともに、地域産業の大きな課題となった人材確保への支援も積極的に進めます。
観光交流面では、こもろ観光局と連携し、地域が持つ小諸市でしか味わえない魅力的な観光を効果的に伝え、ブランド力を活かした情報発信を進め観光誘客を図るとともに、地域資源の活用による新たな観光素材の掘り起こし等観光地域づくりを進め、国内外からの誘客と交流人口の増加に取り組みます。
再整備を進めている動物園は、クラウドファンディングを活用しつつ、第2期整備を着実に実施し、動物も人も楽しく快適に過ごせる魅力ある動物園として、令和8年度に迎える開園100周年を、市民を挙げて祝いたいと思います。
移住・定住促進は、地域産業の人材確保や農ライフと連携した小諸市独自の取組など、年々変化するニーズを的確にとらえた事業展開を進めるとともに、誘致活動や体験事業等のイベントの実施、空き家バンクの運営などは、引き続き民間ノウハウを取り入れて取り組み、人口の社会増につなげてまいります。
5 安心して快適に暮らせるまち「生活基盤整備」
五つ目は、安心して快適に暮らせるまち「生活基盤整備」の分野です。
平成29年に策定した立地適正化計画の評価と見直しを行い、多極ネットワーク型コンパクトシティにより持続可能なまちづくりを推進し、市民生活の利便性の向上と地域の活力を高めるとともに、あらゆる災害を想定した「災害に強いまちづくり」を推進してまいります。
また、生活に欠くことのできない道路や橋梁等の社会基盤の適正な維持管理と長寿命化を図るとともに、水道水の安定供給と持続可能な安定経営を図り、全市民が安心して快適に暮らせるまちづくりを進めてまいります。
交通ネットワークの持続可能な運行とさらなる充実に向け、地域公共交通計画を策定し、「こもろ愛のりくん」の利用促進と運行 改善につながる取組を進めてまいります。鉄道・バス等の幹線交通については、ICカード導入等の支援を行い維持確保に努めます。
小諸駅周辺の取組では、社会実験を通じて駅前広場の再整備計画の策定を進めるとともに、旧小諸本陣・大手門・三之門地区の文化・観光交流拠点化を公民共創により進めてまいります。そして、居心地の良い、歩いて楽しい都市を目指し、公園や文化施設、駅施設など公共空間の活用と外出機会の創出につながる交通サービスを包括的に実施してまいります。
社会基盤整備においては、長寿命化修繕計画に基づき、舗装改良及び橋梁の修繕を実施してまいります。生活道路等の整備については、評価基準に基づいた優先順位により事業を実施するほか、維持補修により生活道路の維持・長寿命化と通行の安全性の確保を図ってまいります。
老朽化が進む市営住宅については、改訂した小諸市公営住宅等長寿命化変更計画に基づき、適正な維持管理に取り組んでまいります。
上水道事業については、公民共同企業体である株式会社水みらい小諸と効率的な水道事業運営に努めてまいります。
また、計画的な施設更新を進めるとともに経営戦略を見直し、経営の基盤強化を図ってまいります。
防災等においては、あらゆる災害を想定した訓練と準備を断続的に実施することで「災害に強いまちづくり」を進め、市民の安全・安心な暮らしを守ります。
災害への備えとして「自助・共助」の啓発に積極的に取り組むとともに、全ての区において機能的、機動的な自主防災組織が設立されるよう働きかけ、地域防災力を向上させます。
また、消防団と自主防災組織の連携災害対応訓練の実施により、地域における防災体制を強化してまいります。
災害情報伝達手段を可能な限り重層化することで、誰もが情報を受け取り、いざという時に自らの判断で行動できるなど、個々の住民の防災力が高いまちを目指してまいります。
また、犯罪や交通事故の被害に遭いやすい子どもや高齢者を対象に関係機関と連携し、防犯教室等の啓発事業を強化し、防犯と交通安全を推進するとともに、消費者トラブルを未然防止・拡大防止するため、身近な相談窓口である消費生活センターが警察などの関係機関と連携し、相談事業と効果的な啓発活動を進めてまいります。
6 すべての主体が参加し、協働するまちづくり「協働・行政経営」
最後、六つ目は、すべての主体が参加し、協働するまちづくり「協働・行政経営」の分野です。
小諸市自治基本条例に謳う「市民一人ひとりが自治の主体であることを自覚するとともに、自らの意思と責任において主体的に行動し、互いに暮らしやすい地域社会を協働で創ること」の重要性に対する理解を深め、各主体の自発的で主体的な活動を活発にします。
コロナ禍において希薄化した地域コミュニティについては、時代に即した地域コミュニティの活性化を目指し、課題の共有をはじめ、区を越えた共同事業や運営管理体制の構築を、地域の主体性を大切にしながら、地域に寄り添った形で推進します。また、市民や市民団体、企業や大学・高校等と連携を深めるなど、協働のパートナーとしての行政も、その役割を積極的に果たしてまいります。
戦略的で効率的・効果的な行政経営を推進するため、基本計画を基軸とした「行政マネジメントシステム」の継続的な改善と適切な運用を図るとともに、恒常的な事業の見直しと併せて財政計画及び公共施設マネジメントを包含したものとして再構築します。
公共施設マネジメントにおいては、学校再編整備に伴う跡地活用等を含め、住民とのコミュニケーションと合意形成を図ることを基本に、住民サービスに必要な機能の集約化、複合化、多機能化を進めるとともに、遊休施設については、民間企業等への譲渡も含め検討を進め、公共施設の総量削減に取り組みます。
健全な財政運営には歳出のコントロールは欠かせません。学校再編整備等に伴う大型事業が控える中、各分野における事業の全庁的な見直しが必要であるため、費用対効果を十分に検証する中で取捨選択を行い、事業の廃止、縮減を検討してまいります。また、歳出の削減だけではなく、市税をはじめ、ふるさと納税やクラウドファンディングによる寄附金等の自主財源の確保など、歳入を増やすためのアプローチにも積極的に取り組みます。
DXの推進に関しましては、市民の利便性の向上及び庁内業務の効率化を推進し、さらなる市民サービスの向上を図ります。
あらゆる媒体を活用した情報戦略によるシティープロモーションを推進強化し、戦略的・効果的な情報発信に努めるとともに、交流人口、関係人口の創出をきっかけとして、人口の社会増を図り、さらには、人口構造の転換を図ることで自然増へつなげていきます。
市役所が文字通り「市民の役に立つ所」であるよう、引き続き職員の意識改革と市民目線での実践を積み重ね、市政に対する市民満足度を向上させます。
人材育成基本方針の浸透を図るとともに、人事評価システムの適切な運用により、職員のマネジメント能力向上をはじめ、ソーシャルキャピタル(社会的つながり)が高く、自立(自律)し、チャレンジする職員の育成を進めます。
以上、政策分野別に令和7年度における重点施策の一端を述べ させていただきました。
現在、様々な政策・施策の実施が功を奏し、また、市民や関係する皆さま方のご協力により、県内外からも小諸市が注目されるようになりました。そのことを象徴するように東洋経済新報社発表の「住みよさランキング」では26位と上位に位置し、宝島社発表の「住みたい田舎ベストランキング」でも人口3万人以上5万人未満の部で総合8位にランクインするなど、客観的な評価もいただいております。
また、令和6年度の実績でも触れましたが、先日、長野県が発表した令和6年の人口動態においては、首都圏回帰が顕著にみられる中、転出者数等を差し引いた人口の社会増減は、81人の増となり、令和2年から5年連続での人口の社会増が続いています。これは、これまでの間の施策の実施や、関係する皆さまの取組が成果として現れているものと思っております。
一方で、出生者数は一昨年が206人、昨年は224人とこの数年間では少ない数値となっており、この改善が本市における最大の課題であると認識しております。
私は、市長3期目の重要課題として、今後も「選ばれるまちとなること」そして「人口の自然増へ挑戦すること」を市民の皆様に申し上げてまいりました。そして、令和7年の年始には職員への訓示で「挑戦」の二文字を掲げたところです。
これらは、言うは簡単ですが、決して容易なことではないことも承知しており、実現するには、議員はじめ多くの市民、関係者、事業者、団体等の皆様の参加と協働、連携、協力が必要です。
まさに「まちづくりの核は人である」こと。そして、「シビックプライド」を醸成していくことで、小諸のまちは今後も大きく発展していくものと確信しております。
小諸市には、まだまだ課題があります。これらを解決していくためには、熱い想いに裏打ちされた強い決意と覚悟を持って取り組んでいくことが必要です。小諸市がさらに大きく飛躍するため、私もその一員として、市民の皆様そして職員の先頭に立ち、市長としての職責を果たしてまいります。
そして、令和7年度も「小諸版ウエルネスシティ~第2章~」を旗印に、市民や小諸を訪れる人が?ウエルビーイング(幸福で肉体的、精神的、社会的に全てに満たされた状態)?となるような小諸を目指し、誠心誠意そして全力で取り組んでまいります。
市民の皆様には、引き続き小諸市政の推進に一層のご理解と ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げ、令和7年度の施政 方針といたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
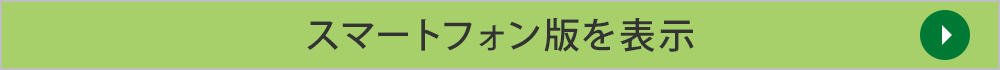
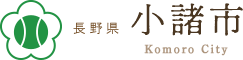
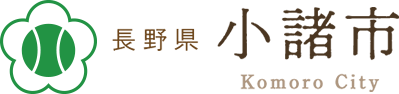

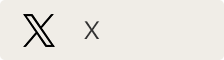


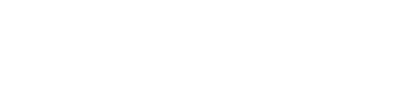

更新日:2025年02月28日