所信表明
小諸市議会における、小泉市長の所信表明を掲載します。
所信表明 令和6年6月 (PDFファイル: 389.9KB)
6年6月10日
小諸市議会6月定例会
令 和 6 年 度
所 信 表 明
小諸市長 小 泉 俊 博
令和6年小諸市議会6月定例会の初日にあたり、私の所信の一端を申し述べさせていただき、議員の皆様並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
私は、去る4月7日執行の市長選挙におきまして、多くの市民の皆様のご支持をいただき、三度、小諸市政の舵取りの重責を担わせていただくこととなりました。
あらためまして、市民の皆様に厚く御礼を申し上げますとともに、私にお寄せいただきました多くのご期待にお応えするべく、3期目も力の限りを尽くして、誠心誠意、市政経営に邁進いたしますことをここにお誓い申し上げます。
議員の皆様には、引き続き、ご指導、ご鞭撻を切にお願い申し上げます。
目指すまちづくりの方針
昨今、市内外の方から「今の小諸には勢いがある、元気がある。」と言われることが多くなりました。これを裏付けるように、客観的なデータを基に東洋経済新報社が集計している2023都市データパックにおいて小諸市は、全国812の都市の内、「住みよさランキング」で25位(2022年33位・2021年171位)となりました。
また、実際に、人口動態においても大幅な転入超過が続いている状況を背景に、マスコミ等で本市のまちづくりの取組みや地域活動、特色ある企業、個店等の進出が取り上げられることが増えるなど、全国から注目を集めるようになりました。
これら本市の元気や勢いは、多くの市民や団体、企業、関係機関等が連携協力の下、小諸のアイデンティティを大切にしながら共に汗水流してまちづくりに取り組み、その積み重ねが、今、成果として見える形で現れてきているものと考えております。
一方で、少子高齢化・人口減少の進行、厳しさを増す地方財政、魅力や特性を生かした地域づくり、脱炭素社会の早期実現、防災・減災による安全・安心のまちづくりなど、地方自治の維持・発展には多くの課題もあります。
引き続き、健幸都市こもろ「小諸版ウエルネス・シティ~第2章」として「あらゆる分野で健康・健全で自己実現できるまち、自分に還る・何度でも帰りたいまち、住みたい・住み続けたいまち」を小諸市のあり方・ビジョンとして掲げ、まちづくりの施策を展開してまいります。
そして、これらを具現化した姿として、子どもから高齢者まで皆が健康で生きがいを持ち、安全・安心で豊かな人生を営み、最後まで自分らしく人生を全うできる地域社会の実現に鋭意取り組んでまいります。
特に、深刻化する人口減少と少子化問題に対処するために「自然増(死亡者数より出生者数が多い状態)への挑戦」として「若者がくらしやすいまちづくり」「子育てが楽しいまちづくり」「子ども・女性を大切にするまちづくり」は、差し迫った直近の課題として捉え、力を傾注いたします。
それでは、ここからは、私の基本政策及びその実現のための重点施策をご説明申し上げます。なお、現在、策定を進めている小諸市総合計画第12次基本計画に合わせて6つの政策の柱にまとめましたのでよろしくお願いします。
1 心豊かで自立した人が育つまち「子育て・教育」
まず、一つ目は、心豊かで自立した人が育つまち「子育て・教育」の分野です。
子どもたちの「学びに対する意欲や喜び」を高め、基礎学力の向上とともに、問題解決的な学習を通して、自ら考え行動できる力を育成し、すべての学びの場を通して「自己肯定感」の醸成に努めます。そして、「確かな学力」「豊かな人間性」「たくましく生きるための健康や体力」の総体である「生きる力」の育成を図ります。
子どもたちの学びを適切に支えるため、子育て世代に、より良い子育て環境や教育環境を提供します。特に小学校低学年で国語学習を充実させ、基礎学力の確立につなげます。
子どもたち一人ひとりに新たな時代を生き抜くために必要な資質・能力が身につくよう、小諸市全体で小中一貫教育を推進し、本市の教育が目指す学校づくりに取り組んでまいります。その中で、昨年7月にまとめた学校再編計画に基づき、芦原中学校区では、令和10年度の開校を目指した統合小学校の学校建設、学校運営の検討を進め、小諸東中学校区においては、当面、既存校舎の計画的な大規模改修等を実施しながら、小中一貫教育の具体の検討を進めます。
小諸市が誇る安全で美味しい「自校給食」の継続と安定的な運営に引き続き取り組んでまいります。
子どもと子育て家庭の総合窓口として本年度設置した「こども家庭センター」において、家庭における子育ての負担や不安、孤立感を和らげ、安心して子育てができる環境づくりを、行政と家庭や地域が連携し、社会全体で取り組む体制づくりを確立してまいります。特に、保育園においては、未満児保育ニーズに対応できるよう保育人材の確保に努めるとともに、保育環境の充実を図ります。さらに、将来にわたりより良い保育環境が提供できるよう、保育園の再配置計画の策定を進めます。
文化財、生涯学習については、市民の主体的な「学び」を促進するため、ニーズを捉えた学習機会の創出や、快適に利用できる施設環境の整備に取り組みます。また、小諸の歴史的、文化的なお宝や自然の素晴らしさなどを楽しみながら体験する「ふるさと学習」を推進し、ふるさとを愛し大切に思う郷土愛溢れた子どもの育成に努めます。
「音楽のまち・こもろ」では、引き続き小中学校の音楽活動を推奨するとともに、これまで実施してきた事業の創意工夫と見直しにより、あらゆる世代における音楽文化の発展を図ってまいります。
旧小諸本陣の修理復原工事では、着実に工事を進めるとともに、観光面とのつながりを深めるなど、積極的な有効活用を図ります。また、小諸城址懐古園の名勝指定は、国指定を目指し、その前段として県指定の準備を進めてまいります。旧北国街道沿いの小諸宿の歴史的町並み形成については、保存だけでなく、積極的な活用により、まちづくりにつなげることを基本とし、地元と連携協力しながら地域の合意形成など、丁寧に進めていきます。
スポーツについては、多様なスポーツニーズに応じた機会の充実により、市民のスポーツ振興を図ってまいります。特に子どもたちにとっての運動は、生涯スポーツの基礎となり、育ちの一助となります。高地トレーニングで小諸を訪れるアスリートや競技団体と、子どもたち、市民が交流する事業など様々な機会を積極的につくり、スポーツを身近に感じる取組みを進めてまいります。
また、長野県で開催される2028年国民スポーツ大会では、小諸を舞台としたレスリング競技の成功に向けて、新設した国民スポーツ大会準備室を中心に長野県や長野県レスリング協会など、関係団体と連携を密にしながら着実に準備を進め、併せて、気運を醸成し、市民のスポーツへの関心を高めてまいります。
人権関係については、人権及び男女共同参画に係る次期計画を策定し、すべての家庭・職場・地域における社会人権同和教育や学校人権同和教育、各種研修会、啓発活動を計画的かつ積極的に推進し、子ども、女性、外国人、性の多様性、同和問題、インターネット上の人権侵害など、あらゆる人権問題に対する正しい理解と認識を高め、市民の人権尊重意識の高揚を図ります。また、男女共同参画及びジェンダー平等社会の実現を目指します。
なお、小諸市第12次基本計画の策定に合わせて、「第3期こもろ未来プロジェクト教育編(小諸市教育大綱及び小諸市教育振興基本計画)」を策定いたします。
2 豊かな自然と環境を未来につなぐまち「環境」
二つ目は、豊かな自然と環境を未来につなぐまち「環境」の分野です。
豊かな自然環境を守り、生活環境を保全するとともに、資源循環型社会の形成を図ります。
また、地球温暖化防止に努め、自然環境にやさしいまちづくりを進めます。そのために、市民、事業者、行政が環境に対する意識をさらに高め、それぞれの役割と責任を意識し、省エネルギーの徹底や環境、景観、地域との調和を図りながら、再生可能エネルギーの活用を推進し、温室効果ガスの削減に取り組みます。
そして、市民の自発的、主体的な行動を促進するための助成や、脱炭素先行地域づくり事業を実施してまいります。
さらに、地域との合意が形成され、自然環境と調和した再生可能エネルギーの普及を図るため「太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」を厳格に運用します。
新たに策定した「第3次環境基本計画」及び「第2次ごみ処理基本計画」に基づき、良好な自然環境及び生活環境を維持、保全してまいります。特に、地球温暖化防止、ゼロカーボンの実現へ向け「小諸市ゼロカーボン戦略推進本部」を中心に、基本協定を締結している企業や各種団体の皆様と連携協力しながら、市民への情報提供と啓発を進めます。
また、「動植物の保護に関する条例」を適切に運用すること等で、市民意識の高揚を図り、本市の豊かな自然環境の保全を図ります。
下水道事業においては、利用者の意向との調整等から、未普及地域内の整備方針を見直すとともに、効果的な普及促進活動を模索しながら拡大に努め、施設整備の概成と使用料収入の維持・拡大を図ります。そして、処理区統合を推進するとともに、「ストックマネジメント計画」の実行とあわせて事業の経営基盤強化を図ります。
3 全ての人のいのちが輝くまち「健康・福祉」
三つ目は、全ての人のいのちが輝くまち「健康・福祉」の分野です。
市民の誰もがいのちを大切にし、いのちが大切にされ、子どもから高齢者まで皆が健康で生きがいを持ち、最後まで自分らしく心豊かに人生を全うできるような地域社会を創ってまいります。
第4次小諸市健康づくり計画「げんき小諸21」に基づき、関係組織や協力団体と連携しながら、食育や、健診受診、こもろ健幸マイレージへの参加等、健康に良い生活習慣の定着を推進します。
また、悩みや困難を抱えた時に助けを求めることができ、一人ひとりの命が大切にされるまちを目指し、ゲートキーパーの養成や
がんとの共生事業にも、引き続き力を入れてまいります。
地域医療体制の維持に向けては、医療の適正利用への啓発を行うとともに、救急医療をはじめとする医療資源に対し、必要な支援を行います。
母子保健を通じて全ての妊産婦、乳幼児等へ関わり、必要な家庭にしっかり支援が届くよう、「こども家庭センター」において保健と福祉の連携を一層強化し、切れ目ない支援につないでいきます。
誰もが生きがいを持って自分らしく暮らせるよう、地域福祉計画・地域福祉活動計画に沿って地域福祉施策を推進するほか、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく福祉サービスの提供や、通所支援等の提供体制の整備を進めます。
生活困窮・子どもの貧困、生活保護等の様々な相談に対し、庁内関係部署及び関係機関が連携と協調による支援を強化するなど、重層的支援体制の整備を進めます。また、地域福祉の要である民生児童委員の活動支援体制の強化を図ってまいります。
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、引き続き地域包括ケアシステムの構築を推進し、高齢者を支える地域のネットワークの拡充を図ります。また、高齢者福祉センター「こもれび」を拠点とした介護予防事業を開催するとともに、これまでも力を入れてきた各区の高齢者の通いの場の開催が継続できるよう、引き続き支援してまいります。
要介護認定率が長年にわたり国・県と比較し、低く抑えられている本市の状況を今後も維持できるよう、フレイル(虚弱)の要因である低栄養、口腔機能や運動機能の低下のリスクや生活習慣病がある高齢者を対象に保健指導を充実させることで、疾病の重症化予防、要介護状態となることの予防につなげ、健康寿命の延伸を図ってまいります。
高齢者が自らの経験や知見、趣味などを通じ、生きがい・やりがいを実感しながら社会参加できる仕組みを構築します。
4 稼ぐ力をもった元気なまち「産業・交流」
四つ目は、稼ぐ力をもった元気なまち「産業・交流」の分野です。
豊かな暮らしを実現するために、「稼ぐ力」を意識した戦略的な産業振興を推進し、「商都・農都・住都こもろ」に向けて力強く取組みます。
農業振興については、農業が「儲かり夢が持てる産業」となることが、後継者や担い手不足の解消につながることから、引き続き「KOMORO AGRISHIFT PROJECT」による農産物のブランド化と、産地規模拡大に向けた取組みを進めます。そして、小諸の豊かで高品質な農産物が良質な「食」につながることをあらためて認識し、新たな品目の普及・定着を目指した経営体育成や栽培方法の検討など、特に中山間地域農業の収益向上に向けた取組みを推進します。
他に先駆けて取組みをはじめた「農ライフ」については、移住施策との組み合わせで推進し、農地の利用促進と遊休荒廃農地の解消につなげていきます。また、ワイン振興については、国内はもとより海外でも高まっている認知度をさらに向上させ、高品質ワインの産地として、その地位を確固たるものにするための事業を展開してまいります。
安定的な農業経営に欠かせない優良農地は、良好な状態で次の担い手に引き継ぐため、ほ場整備エリア内の農業用施設の維持補修を計画的に進めるとともに、大規模な整備や改修が必要な農道や水路等は、防災減災対策を含め補助事業を有効に活用しながら事業を推進します。
ゼロカーボンの取組みにおいても重要な森林整備は、森林環境譲与税や森林づくり県民税などの財源を有効活用し、森林整備実施方針に基づき計画的な整備を進めるほか、野生鳥獣被害対策を安定的に実施してまいります。
商工業振興は、引き続き地域の強みを活かした、積極的な企業誘致に取り組むほか、既存企業・事業者の支援も強化します。さらに、新産業団地整備を着実に進めるとともに、商工会議所との連携を深め、起業・創業への支援を強化することで、市内への投資促進はもとより、経済やまちづくりの担い手の誘致・育成に取り組んでまいります。また、デジタル技術の活用による、子育てがしやすい働き方ができるまちを目指し、関係機関と連携し取り組みます。
観光交流面では、こもろ観光局と連携し、歴史遺産や自然環境等、地域が持つ魅力を効果的に発信し、認知度の高まりとともに、ブランド化の進む地域資源を積極的に活かし、国内外からの誘客と交流人口の増加に取り組みます。
再整備を進めている動物園は、第2期整備を着実に実施し、動物も人も楽しく快適に過ごせる魅力ある動物園として、令和8年度に迎える開園100周年を、市民を挙げて祝いたいと思います。
移住・定住促進は、地域産業の人材確保や農ライフと連携した小諸市独自の取組みなど、年々変化するニーズを的確にとらえた事業展開を進めるとともに、誘致活動や体験事業等のイベントの実施、空き家バンクの運営などは、引き続き民間ノウハウを取り入れて取り組み、人口の社会増につなげてまいります。
5 安全・安心で暮らしやすいまち「生活基盤整備」
五つ目は、安全・安心で暮らしやすいまち「生活基盤整備」の分野です。
多極ネットワーク型コンパクトシティのまちづくりを推進し、まちなかに都市機能を誘導するとともに、高齢化社会にあっても公共交通を使った一度の外出で用事が足りるなど、市域全体の利便性を高め、皆が住み慣れた地域で、安心して快適に暮らせるまちを目指します。
交通ネットワークの持続可能な運行とさらなる充実に向け、市内公共交通においては「こもろ愛のりくん」の利便性と効率性の両立を目指し、運行改善を継続的に図ります。そして、鉄道・バス等の幹線交通の維持のための支援や交通と情報発信を連動させた電動カートの運行など、環境にもやさしい利用者本位の交通ネットワークシステムの構築を推進します。
小諸駅周辺の取組みでは、社会実験を通じて駅前広場の再整備計画の策定を進めるとともに、旧小諸本陣一帯の文化・観光交流拠点化を公民協創により進めます。そして、居心地の良い、歩いて楽しい都市づくりとしての付加価値を高めるため、公園や文化施設、駅施設など公共空間の活用と外出機会の創出につながる公共交通の利用促進を包括的に実施します。
社会基盤整備においては、長寿命化修繕計画に基づき、舗装改良及び橋梁・トンネルの修繕を実施します。生活道路等の整備については、評価基準に基づいた優先順位により事業を実施するほか、維持補修により生活道路の維持・長寿命化と通行の安全性の確保を図ります。
老朽化が進む市営住宅については、改訂した小諸市公営住宅等長寿命化変更計画に基づき、適正な維持管理に取り組んでまいります。
上水道事業については、公民共同企業体である株式会社水みらい小諸と効率的な水道事業運営に努めるほか、100周年を契機に、安全で良質な本市の水の魅力発信に努めます。また、計画的な施設更新を進めるとともに、経営戦略を見直し経営の基盤強化を図ります。
防災等においては、あらゆる災害を想定した訓練と準備を断続的に実施することで「災害に強いまちづくり」を進め、市民の安全・安心な暮らしを守ります。
災害への備えとして「自助・共助」の啓発に積極的に取り組むとともに、全ての区において機能的、機動的な自主防災組織が設立されるよう働きかけ、地域防災力を向上させます。また、消防団と自主防災組織との連携した災害対応訓練の実施により、地域における防災体制を強化します。
災害情報伝達手段を可能な限り重層化することで、誰もが情報を受け取り、いざという時に自らの判断で行動できるなど、個々の住民の防災力が高いまちを目指します。
また、犯罪や交通事故の被害に遭いやすい子どもや高齢者を対象に関係機関と連携し、防犯教室等の啓発事業を強化し、防犯と交通安全を推進します。
6 市民協働で支える健全な行政経営「協働・行政経営」
最後、六つ目は、市民協働で支える健全な行政経営「協働・行政経営」の分野です。
小諸市自治基本条例に謳う「市民一人ひとりが自治の主体であることを自覚するとともに、自らの意思と責任において主体的に行動し、互いに暮らしやすい地域社会を協働で創ること」の重要性に対する理解を深め、各主体の自発的で主体的な活動を活発にします。
ウイズコロナの時代に即した地域コミュニティの活性化を目指し、課題の共有をはじめ、区を越えた共同事業や運営管理体制の構築を、地域の主体性を大切にしながら、地域に寄り添った形で推進します。また、市民や市民団体、企業や大学・高校等と連携を深めるなど、協働のパートナーとしての行政も、その役割を積極的に果たしてまいります。
第12次基本計画の策定については、施策の実現性や事業の実効性を確保するため、財政計画を策定し、それに即した行政マネジメントシステムの運用を再構築するとともに、持続可能な自治体であるための新たな予算編成手法の確立に取り組んでまいります。
公共施設マネジメントにおいては、学校再編整備に伴う跡地活用等を含め、住民とのコミュニケーションと合意形成を図ることを基本に、住民サービスに必要な機能の集約化、複合化、多機能化を進めながら公共施設の総量削減に取り組みます。
健全な財政運営には歳出のコントロールは欠かせませんが、それだけではなく、市税をはじめ、ふるさと納税やクラウドファンディングによる寄附金等の自主財源の確保など、歳入を増やすためのアプローチにも積極的に取り組みます。
DXを手段として、市民の利便性の向上及び庁内業務の効率化を推進し、さらなる市民サービスの向上を図ります。
情報戦略によるシティープロモーションを推進強化し、交流人口、関係人口の創出をきっかけとし、人口の社会増を図り、さらに、人口構造の転換を図ることで自然増へつなげていきます。
市役所が文字通り「市民の役に立つ所」であるよう、引き続き職員の意識改革と市民目線での実践を積み重ね、市政に対する市民満足度を向上させます。
人材育成基本方針の浸透を図るとともに、人事評価システムの適切な運用により、職員のマネジメント能力向上をはじめ、ソーシャルキャピタル(社会的つながり)が高く、自立(自律)し、チャレンジする職員の育成を進めます。
以上、市長3期目に向けた私の基本政策及びその実現のための重点施策を申し上げました。
目指すまちづくりの重点政策
今の小諸の変化は、市民をはじめ各種団体や企業など、関係する皆様の努力が一つひとつ積み重なったことにより、化学反応が起き、良いスパイラルが生まれた結果だと考えております。
さて、本市の令和5年の人口動態においては、転入者数は、過去8年間で最多の1,847人で、転出者数等を差し引いた人口の社会増は、前年を大きく上回る289人となりました。この結果、昨年中の人口減少は、この8年間で最も少ない98人まで抑制され、この間の取組みの効果が現れてきていると言えます。
一方で、出生者数は206人と、この8年間では最も少ない数値となり、この改善が、本市のこれからのまちづくりにおける最大の課題であると認識しているところでございます。
私は、今回の市長選挙を通じ、一貫して、今後も「選ばれるまちとなること」そして「人口の自然増へ挑戦すること」を市民の皆様に申し上げてまいりました。
これは、言うは簡単ですが、決して容易なことではないことも承知しており、実現するには、並々ならぬ覚悟と決意が必要だとも考えています。
時代とともに変化する若者の考え方やニーズに目を向け、一人ひとりが自分らしい生き方や働き方が選択できるようにすること。子どもが自立するまでを一緒に支える地域づくりや、親が安心して子育てができ、子ども自身も安心して過ごせる環境があること。誰もが性による社会的・文化的差別やDVを受けることなく過ごせ、医療や福祉、産後ケアの充実とともに子どもの育ちへの権利が擁護されていること。産前・産後の支援が充実するよう、父親に対しても多角的なアプローチと相談ネットワークなどの横断的な体制があり、男性の家事育児への参画が活発であること。全世代参加の地域づくりと、時代とともに変わる考え方やニーズに対し、継続性のある次世代を見据えた組織づくりを進めることなど、取組みは多岐にわたる上に、非常にハードルが高いものもあると思いますが、これらを積極的に進めることにより、人口の自然増へ果敢に挑戦してまいります。
このまちの「伸びしろ」は無限大です。あらためて「まちづくりの核は人であること」を強く意識し、「シビックプライド」を醸成していくことで、小諸のまちは、さらに発展していくものと確信しております。
そのためには、変わることを恐れず、常に時代に柔軟に対応しながら、次の世代の「小諸人」のために、決して歩みを止めてはなりません。
小諸市が将来に向けて大きく飛躍するため、私もその一員として、市民の皆様そして職員の先頭に立ち、市長としての職責を果たすべく全身全霊を捧げてまいります。
市民の皆様、議員の皆様、小諸市の明るい未来を切り拓くための歩みを、どうか私と共に、進めていただきますことを心からお願い申し上げ、市長3期目の所信表明といたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
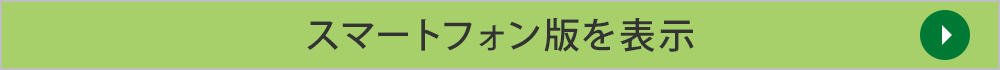
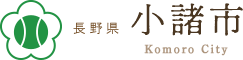
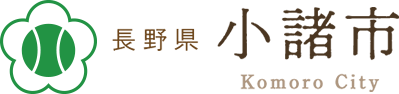

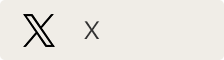


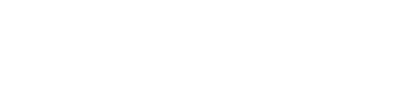

更新日:2024年06月10日