小諸市小中一貫教育推進基本方針を策定しました(令和6年9月)
小諸市教育委員会では、次のとおり小諸市小中一貫教育推進基本方針を策定いたしました。
本ページでは、基本方針本文より抜粋した内容を記載します。
基本方針説明動画(9分20秒)
令和6年11月に開催いたしました市民説明会「小諸市小中一貫教育推進基本方針」の内容を、動画にて説明いたします。
1 教育ビジョンの策定について
・小中一貫教育の推進にあたり「拠り所」となる理念である「小諸市小中一貫教育ビジョン」を策定しました。
2 小諸市学校教育目標について
現状の洗い出し及び考察を受けて、小諸市としてどのような子どもたちを育てたいのかを「小諸市教育大綱」の基本理念に基づき、「小諸市学校教育目標」として次のように定めました。
心豊かで、自立(律)する子どもの育成
3 小中一貫教育推進のための視点
1.「対話と協働」の学びの推進
教員の話を聞くことを中心とした、これまでの「一斉授業」から小グループ等で対話的・協働的に子ども同士で学び合う授業(「対話と協働の学び」)へ転換していきます。
2.子どもを主人公にした自治的・創造的な学校風土の醸成
子どもが学校の主人公であるために、児童会・生徒会を中心に、様々な場面において子どもたちの「声」が生かされ、子どもの思いや願いが学校運営に反映される学校づくりが必要だと考えています。子どもによる発案を、教職員と子どもで協働的に具現していくという積み重ねの中で、「子ども主体」という学校風土が醸成されていきます。
教職員が直接指導するのでなく、子ども同士で必要なことを伝え合い、あるべき姿を求め合っていく「自治的な学校」において、一人一人の子どもが「自治的・創造的な能力」を身につけ、自らの生き方として様々な事柄に対して「当事者意識」をもって臨んでいくような構えを身につけていくことを目指していきます。
3.すべての子どもを包み込む居心地のよい学校づくり
子どもたちの中には、様々な理由で、学校という場に馴染みにくくなる子どもがいます。そのため、多様性を認め合うことを基盤にしながらも、不適応状況の早期発見・対応に努める必要があります。
そこで、校内支援チームを中心とした校内の情報共有と連携による継続的な支援を進めます。さらに、学級編成や教職員配置等、発達段階に応じた柔軟な指導体制の工夫を行います。
4 ビジョンの具現に迫るために
一つの学校 一人の校長
・小諸市全校で対話と協働の学びを推進するためには、9年間この学び方で貫くと同時に、全教科領域でこの学び方を取り入れていく必要があります。しかし、小中別々の学校では、校種の違いによる優先事項の不一致や置かれている立場の違いにより、この推進がスムーズにいかない可能性があります。そこで、一人の校長の学校運営方針とリーダーシップにより、学校が一丸となって進めることで、小中の垣根を超え、ビジョンのスムーズな具現が期待されます。
・「小学校教科担任制」のような、複数、チーム体制で対応していく組織体制への転換についても、小中が別々の学校だと、それぞれの事情が優先され「授業の相互乗り入れ」といった教科担任制に必要な人員の配置が進まないことが危惧されます。そのため、小中の垣根を超えた弾力的な教職員配置、活用が必須であり、一人の校長の小中全体を見据えた組織マネジメントにより、教科担任制に必要な校内人事を行う必要があります。
・学校をチーム体制で対応していく組織へ変換するためには、多くの教職員の柔軟な配置が必要となります。そのためには、小規模の学校に散らばっていた人材を一つの学校に集め、その中で適材適所に人員を配置していく組織マネジメントが必要となります。教職員の配置には児童生徒数が基準となるため、教職員を集中配置するためには、児童生徒数が一定以上の小中一つの学校である必要があります。
・児童生徒に課題等が発生した場合に、小学校の様子を知る担任が関係者会議に加われたり、経験豊富な中学の教職員がアドバイスできたりするなど、小中の垣根無く継続的に複数の眼で対応に取り組むことができるのは、施設一体型の大きなメリットとなります。
・小中が一つの学校になることで、最大9年の年齢差がある子どもたちが、同じ時と場所を共有し生活するからこそ起こる、日常的で自然な「居ながらの交流」が期待されます。学校行事等による「設えた交流」とも合わせ、上級生と下級生の関係性を活かした交流の中で、自治的・創造的な学校文化が醸成され、それが学校の風土として根づいていくと思われます。
以上のことから、小諸市教育委員会では、「小諸市小中一貫教育ビジョンに示した視点の具現を推進していくためには、施設一体型の義務教育学校を市内全校で目指すことが必要である。」という結論に達しました。
5小諸市全体の小中一貫教育推進の方向性と中学校区間の段階的な対応
1.芦原中学校区
・芦原新校については、令和10年度の開校時に「義務教育学校」とします。
・今後、芦原新校の開校に向け「組織づくり」「教育課程」「学校行事」等を決定するための「ワーキンググループ」を立ち上げ、具体的な学校づくりに取りかかっていきます。
2.小諸東中学校区
・財政面や労力面等で、芦原中学校区と同時進行は困難なため、芦原新校の進捗状況を見据えながらしかるべき準備の後に義務教育学校を目指します。
「小諸の子どもはすべて義務教育学校において育んでいく」ことを目指します。
・小諸東中学校区がそのまま一つの義務教育学校となる「芦原方式」で進めた場合、1校の児童生徒数が1,600人前後となり、運営を考えると難しい面があります。そのような状況を踏まえ、どのように義務教育学校にしていくかについて、今後検討を深めていきます。
・方向性を示すまでの間は、「小諸市小中一貫教育ビジョン」に沿い、小中学校が学校組織やカリキュラム、行事を可能な範囲で揃える方向で進め、義務教育学校としていく準備を進めていきます。
・「小中」「小小」共通の行事や交流の機会を設けていき、多様な他者とのかかわりによる教育効果を享受できる機会としていきます。
・人的な配置や施設設備等、義務教育学校に向けていく中で、分離の状況であっても有効だと思われる方策については取り入れていきます。
6 計画全文
小諸市小中一貫教育推進基本方針 (PDFファイル: 1.2MB)
7 これまでの検討経緯
これまでの検討経緯については、次のリンク先からご確認ください。
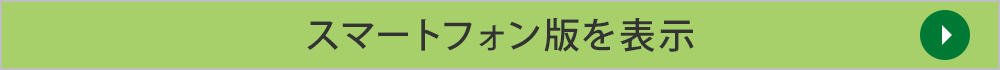
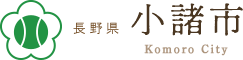
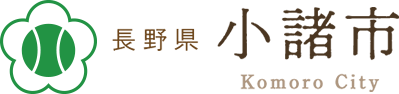

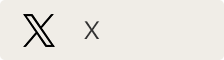


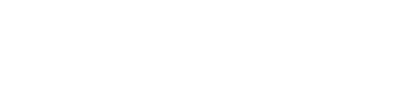

更新日:2024年10月11日