第21回小諸・藤村文学賞 一般の部最優秀賞
メゾン・ド・ヌルーパス
砂田実法
二十五歳から三年間、山深い信州でも、それはそれは山奥の、老舗温泉旅館に住み込みで働いた。仙人が出そうな、霞の中だった。バスはだらだらと一本道をひたすら上って行く。最後に人里を見かけてから一時間ほども走って、とうとう道の果てるドン突きに、思い出の詰まったその旅館は建っている。
射的場なんかのある賑やかな温泉街とはほど遠い。私のように車を持たない従業員には、ほとんど軟禁生活である。夜も提灯一つないこの温泉街だから、外へ出ると、世界には自分と、夜と、億千万の星の他に何もなくなってしまう。今となれば、こんな、世界から忘れられたような、美しい静けさの中で過ごす一日が、都会から来るお客さんにとって何万円もの価値に匹敵することが良くわかるが、たまに来るのと住むのとでは、心持ちは大違いだ。ただでさえ、過酷で離職率の高い宿泊業界で、こんな不便な土地ならなおのこと、つづく人は少ない。私はフロントで働いていたが、仲居さんなんかは、短期派遣の若い女の子が多かった。市街へ出て行かれるのは十日に一度。朝は早いし夜は遅い。職場の中に住んでいるから、ストレスも溜まる。「あいつ出勤してこないな」と言って誰かが寮を見に行くと、もぬけの殻ということもしばしばだった。それでも私は辞める訳にいかなかった。病気をしていた数年間で溜まってしまった借金を、返さなければならなかったのだ。
親友ができた。
彼女は私より半年遅れて旅館にやって来て、寮では私の隣人になった。ふつう、親友というと、何でも話せる間柄だったり、考え方が似ていたりするものだが、ちょっと違う。私は開けっぴろげだが、彼女は自分のことを話したがらない。お喋りだし、懐っこいが、秘密主義を貫いている。国立の中でもかなり優秀な大学を出ている彼女が、東京の一流企業を辞めて仲居さんをしに(それも期間限定ではなく)山奥へ来たなんて、どういう事情だろう。その辺は今もって、ぼんやりしている。
ひと言で表すとしたら、彼女は何しろ、ものすごく変わり者だった。気分がくさくさすると、部屋にこもって因数分解の問題集を何時間も解き続けるような人だ。ファッションにも音楽にも興味がまるでない。眼鏡を外すと実は可愛らしい二重だということを私は知っているのだが、もちろんメイクにもこだわりがない。持ち物は極端に少なくて、着る物は制服と、寝間着と、外出着が上下ワンセットだけ。東京時代のアパートを借りたままにしておいて、かと言ってそこへは年に四度しか行かないのである。
「今日は東京へ行ってきます」
「ああ、着替えに行くのね」
一般に衣替えの季節と言われる時期に、私たちが交わす会話である。半袖から長袖に。薄着から厚着に。ワンセットしかない外出着を、取り換えに行くのだ。体ごと衣替えして、彼女はその日のうちに帰ってくる。
ほとんど右脳だけを頼りに生きている私にとって、彼女の発達した左脳との出会いは衝撃的だった。よく、難しい物理や化学の法則を教えてくれた。宇宙のしくみも、素粒子の次元から解説してくれる。私にはそれがとても新鮮な楽しみだったのだが、話の終着点になると、私たちは何も共有できなかった。
「ヒトは二足歩行を始めてここまで進化したけど、そのせいで産みの苦しみを知ったんやって」
と教えてくれた時も。
「地球と同じ星が存在する確率は、時計をバラバラにして、箱ん中に入れてガチャガチャ振り回して、開けたら元通りになってる確率と同じなんやって」と教えてくれた時も。
私がどんなに力いっぱい感動を伝えても、彼女はただ、目を丸くして私を見ている。
「紅葉がみごとだね」
「私には植物のアポトーシスとしか思えん」
「ああ、桜が満開だよ」
「これ見よがしに咲きよるし、散らかすから嫌い。けど、エントロピー増大の法則にはよう適ってる」
こんな調子である。彼女には、情操面で著しく何かが欠けていた。科学には詳しいが、その奥にロマンを見ることはないのである。そもそもロマンなんて「数式で説明のつかん」ものに関心はないらしい。だから、価値観を交換する類の会話は全く成り立たなかった。それでいて、彼女が私を好きなことは、私にも良く分かっていた。どうしてこんなに心が通ったのだろう。二人でいるといつも笑い転げていた。私は彼女を変な人だといつも言っていたし、彼女も私に同じことを言った。
ある時から私たちは、ペーパークラフト作りに没頭し出した。ぱっと見て、紙とは思えない精巧なモデルである。親友は頭が良いので、複雑な形も型紙に起こすことができる。乗り物、ロケット、沢山の動物。もう作るものがなくなると、動物を住ませる三階建てのアパートをダンボールでこしらえた。
「メゾン・ド・ヌルーパス」
これが、アパートの名前である。ヌルーパスという造語には、意味や由来は何もない。屋上にはヘリポートがあり、ワンフロアに三匹の動物が住める。私たちの中には、大事なものはみんな冷蔵庫、という決まりがあった。開けるといつも、二人で作った、またはこれから作る何かの部品とか、かけらとか、そんな物がこぼれ落ちてくる。宝箱みたいな、仏壇みたいな役割だろうか。ヌルーパスも、廊下の共同で使う冷蔵庫の上に飾られた。
休日だった。親友が衣替えで東京に行っていた。私は寮にこもって、ヌルーパスの外壁工事を、レストランで大量に出るコルクで施し、内装やカーテンを、申し出がなくてゴミ箱行きが決まったお客さんの忘れ物のハンカチで作った。観葉植物も額も飾った。東京から帰った親友の、驚き喜ぶ顔を見て、その日は床に就いた。ところがどうだろう。朝起きてヌルーパスを見に行くと、なんと各フロアにほの明るい照明設備が施されているではないか。東京で買ってきた豆電球を、彼女は夜なべで配線工事していたのだという。こうして、大手玩具メーカー顔負けの一大ミニチュアは出来上がった。他にも二年半かけて、あらゆる模型が寮の廊下を埋め尽くした。一緒に作ることもあったが、大抵は新作を夜中にこっそり廊下の窓辺に置いておく。朝、それを見つけ、嬉しくなって友だちの部屋のドアを叩く。それがいつからか習慣になっていた。周りからは二人とも変人扱いされていたが、私たちの創作意欲は、誰にも止められなかった。
ある日、旅館に警察が来た。私の親友に、捜索願が出されているという。捜しているのは九州のお父さんで、捜し当てられた本人は、捜索願を出した人に連絡をしなければならない決まりがあるとのことだった。いつも強気で、絶対に人に借りを作りたくない彼女が、この時だけ、私にお願いごとをした。
「父に電話をかけるので、そばにいてほしいんですけど」
一度目は失敗に終わった。相手が電話を取った途端、彼女はパニックになって切ってしまったのだ。二度目は間が悪かったのか、留守電。折り返しでかかって来たときには私が傍にいなかったので出ることができなかった。三日目にしてようやく、成功。彼女は、緊張のために体を硬くしていた。「もしもし」と相手が出たのだろう。一瞬ためらった後、実の父親に向かって彼女は名字から名乗った。別に、突っけんどんということもない。
「元気でやっていますので心配しないでください、それじゃ失礼します」
恐ろしく早口に、馬鹿丁寧に告げて一方的に電話を切り、放心したように倒れこんだ。それから「ああ緊張した」と言って彼女は大笑いした。突っ伏したままいつまでもカタカタと体を揺らしていると思ったら、泣いていた。悲しいんだか切ないんだか、怖かったんだか、私にはわからない。気が付いたら私も泣いていた。実家とは疎遠だということは聞いていたが、どんな重荷を抱えていたのか。彼女の身体を擦りながら、手のひらに力をこめて、幸せになれ、幸せになれ、とひたすら祈っていた。
「話すだけで楽になることもあるよ」
そんなことを言っても、無駄だった。結局彼女は最後の日まで、自分の抱えているものが何なのかは、ひと言も打ち明けなかった。
半年後、お互い相談した訳でもないが、同時期に旅館を辞めた。私は借金を清算して、彼女はたぶん、過去を清算した。
今、彼女は遠い海辺の町で、知人の小さな宿泊施設の管理を任され、のびのび暮らしている。東京のアパートも引き払ったようだ。私は母のいる家に帰り、豊かではないけど不自由なく、仕事に追われて暮らしている。
本当は、互いに、清算してゼロに戻した以上の何か大事なものを、あの場所で得たことを知っている。きっと彼女は、一つ、また一つと動物やヘリコプターが出来上がるたびに、過去や不安が昇華されていくのを感じていたのだと思う。そして廊下に新しい模型が増えるごとに、友だちの喜ぶ顔が見られる。これは全く、数式では説明のつかないことだった。
あれから二年になるが、彼女とは文通を続けている。手紙の中身は、相変わらず踏み込んだ内容は何もない。下手すれば、メールでも済む。それでも、私たちがこのアナログなやり取りにこだわるのは、口には出さないけれど同じ理由なのかも知れない。内容はくだらないけれど、ありったけの気持ちを伝えたいから、まめまめしく書き合っている。ポストに手紙を見つけると、廊下に新しい模型を見つけた時のあの気持ちが蘇ってくる。自分をさらけ出すのが苦手だと知っているだけに、私には親友の書くひと文字ひと文字が、自分の殻を破ろうともがいているように思えて、たまらなく愛おしい気持ちになる。
(長野県松本市)
(無断転載を禁ず)
関連記事
平成27年7月8日
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会 文化財・生涯学習課
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
お問い合わせはこちらから

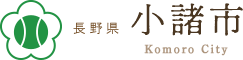


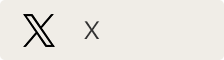


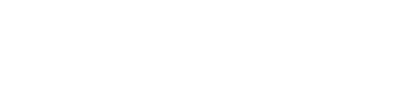

更新日:2019年03月28日