第22回 小諸・藤村文学賞 一般の部最優秀賞作品
第22回 小諸・藤村文学賞 一般の部最優秀賞
母のパーマネント
長田あいゆ
第二次世界大戦敗戦より七、八年たった昭和二十八年ごろは、私の住んでいた岡山の田舎でも頭髪にパーマネントをかけている女性が多く見られるようになった。当然、小、中学校の授業参観日でも、チリチリに髪を縮らせたお母さんたちが多く見られた。
そして身に着けている物も、普段は継ぎを当てたブラウスにもんぺ等の野良着姿のお母さん達だが、ひと度参観日ともなれば、いささか場違いな感じのするような樟脳の匂うメリンスの派手な柄の和服や大きな花柄の銘仙の和服を着ている人や、赤い小花柄の色はきれいだがすぐ皺のよる人絹のハイカラなワンピースを着ている人など様々であったが、私から見ればみな金持ちに見えた。事実、このあたり一帯は牛小屋に牛を飼って耕作用に使い、庭に鶏を放し飼いにして卵を産ませている農家が多く、収穫した米や麦、卵等を、食料を求めて買いに来る都会の人たちに売ったり、上等な衣類や指輪等と物々交換するなどして、戦後、急速に裕福になった家が多かったのである。
もっとも、お婆さん達は「パーマネントをかけた頭は、まるで雀の巣じゃ」などと言って毛嫌いし、相変わらず髪を後頭部で一つに束ね、襟足のところで小さなお団子をつけたように毛束を丸めて、U字形の大きめのピン二、三本で留めていた。洋服にも馴染めないらしく、着ているお年寄りはまだ見かけなかった。数え年六十近くにもなれば、曲がった腰に片手をのせ、片手で杖をついてゆっくりと歩いている人が多く、腰が曲がっているせいで、多くのお婆さん達が身に着けていた鼠色の和服の裾は、両足の間が少し開いて、そこから痩せた足首あたりが見え隠れしていた。そして、その足には自分で編んだ藁草履かゴム草履、または家族が履かなくなった歯のすり減った下駄を履いていた。
中学二年の私達の授業参観に来たお母さん達も、ほとんどがこの日の為に頭髪にチリチリにパーマネントをかけていた。その中で私の母だけは、お婆さんのようにひっつめ髪にして、襟足のところで小さく丸めてピンで留めていた。
酒好きな父は、終戦の年に職場から持ち帰ったメチルアルコールを飲んで盲目となり、同じようにして飲んだ四人の同僚は、亡くなったのだった。
按摩師となった父の僅かな収入と時折入る母の道路人夫の仕事や農作業の手伝いなどの現金収入で、やっと生計をたてている我が家には、そんな余裕などなかったのである。しかし、父の元に来る前は、秋田の大きな温泉旅館の仲居頭をしていたという母は、パーマネントこそかけていなかったが、鼻のあたまにいい匂いのする白粉をはたいて、たった一着だけ、米や麦に替えずによそ行き用に残していた一張羅の大島紬を着た母の姿は、他のどんなお母さんよりきれいだった。思春期の私は、そんな母に反抗しつつも、心密かに誇りに思っていたのである。
そんなある日、私が学校から帰ってくると、母は庭畑で鍬をふるっていた。元々そこは、我が家の裏の小さな空き地であったのを、母が勝手に耕して畑にしてしまったのだ。俗に言う猫の額ほどの小さな畑であったが、母はそこに馬鈴薯や季どきの野菜を植えて、生活の足しにしていたのである。
その庭畑に沿って、細い小川が流れていた。幼い頃の私は、その細い流れに張った薄氷が日射しを返して虹色に光っているのを目にして、また、小川の土手の枯れ草に霜が下りて朝日にキラキラと輝いているのを見て、その美しさに思わず目を見張ったものだった。そして、その土手に続く僅かな枯れ草の根元から、緑色の新芽が伸び始め、その中にその春初めての土筆を見つけた時は、毎年の事ながら胸がときめいた。もう寒い冬は去り、村の所々にある桃山の桃が咲くと、桃山はいっせいに桃色にそまり、その下には黄色の菜の花畑、そして、緑色のジュータンを敷き詰めたような麦畑光景が、脳裏に浮かぶのだ。
その小川をポンと飛び越えると、小川沿いに細い道うねうねと曲がり、途中で消えた所の家の横からすっと姿を現す通行人のほとんどは、農家の人達だった。継ぎの当たった国防色のよれよれの服に、これまた継ぎはぎのくたびれたカーキ色のズボンをはいたおじさんや、日本手ぬぐいを姉さん被りにして、いっぱい継を当てた服を隠すように割烹着を着け、モンペをはいたおばさん達が行き来した。その人たちは小川のそばに立っている私に、
「あいちゃん、そこで何をしょうるんじゃ、どじょうでも見付けたんか」
「ちょっと見ん間に、大きゅうなったなあ」
などと気安く声を掛けてくれた。そのおじさんやおばさん達は、よく一輪車の猫車押していた。それは、車体も車輪も全部が木で出来ている細長い一輪車で、ちょうど猫があるきながら伸びをしている形に似ているように私には見えた。その猫車の背中と見える少しへこんだ部分に収穫した馬鈴薯などをかますという稲藁で編んだ袋に詰め、上手に括りつけて家に持ち帰るのだ。私も一度近所のおばさんに頼んで、猫車を押させて貰った事があったが、どうしても右や左に傾いて、子供の手に負えるものではなかった。このような農村で、しかし、我が家は農家ではないので、農作業はあまりすることなく私は育ったのだった。
手につけた手甲で時折、顔の汗を拭きながら鍬を振るっている母に、
「只今」
と形だけの挨拶をしながら、私は母の顔を見て驚いた。姉さん被りの日本手ぬぐいの下に見え隠れしている母の髪が、短くなって縮れているのであった。私の胸はドキドキして、
(あ、お母ちゃんもとうとうパーマをかけたんじゃな、良かった)
と心の中で思った。
「お帰り」
と、母はいつものようにぶっきらぼうに言ったが、でも、その声は少しはにかんで、いつもよりやさしく私には聞こえた。
今思えば当時の私は思春期の真っ直中で、両親、特に同性の母に対して反抗的で、必要な事以外は、一言も言わない少女だった。母は、私の弟がまだ物心がつかない時にこの家に来たので、義理の母であることを知らない弟ばかりを可愛がっているような気がして、私は多分にひねくれてもいたのであった。そのくせ、何とかして私の事もかまって欲しいと願っているのだが、言動に表れる私は、反抗的でいじけた扱いにくい少女だったと思う。心の中にやり場のない不満、また、反抗心をかかえていて、それはいつか爆発しそうな予感をはらみ、私は、自分で自分をコントロールする自信がないような状況にあった。自分でも可愛くないな、と思いながらも口をついて出る言葉は、とげとげしい反抗的な言葉ばかりであった。私ばかりではない、貧しさ故か、両親もゆがみあい罵りあいながら暮らしていた。そんな暮らしの中で、母が人並みにパーマネントをかけたのだ。私は、嬉しくてならなかった。
その日の夕方のことである。庭畑でとれた薩摩芋をふかした母は、いつもなら、
「芋は夕飯の代わりだ」
とだけ言って、まだ目の見えるころの父が作った木の丸い卓袱台の上に、笊にのせたふかし芋を置いたまま、また、畑仕事や庭掃除をするのだが、その日は違っていた。
「ほれ、旨げに芋がふけたで。みんなで温かいうちに食べようで」
と父や私にも声をかけてくれたのだ。その呼びかけに盲目の父も卓袱台ににじり寄り、
「ほう、ほんまに上手そうな芋の匂いじゃ」
と機嫌の良い声を出して、湯気の立つそれに手を伸ばした。
「あっつ、こりゃ熱いのう」
と小学校四年の弟が、少し大げさにおどけて食べる姿を見て、母が笑った。久しく見た事のなかった母の笑顔とあたりに漂うほのぼのとした空気に、私は何も言葉にする事は出来なかったが、これが家庭の温かさだと、思わず涙ぐみそうになったのを覚えている。
そして、次の日もその次の日も、母はいつもより父にも私にも優しくなったような気がした。
貧しさと忙しさに、優しさも失ったかのように見えた母に、あの温もりを取り戻してくれたのは、どんなきっかけで心境の変化があったにせよ、一人の女性に立ち返り、パーマネントをかけた母のおしゃれ心のように、私には思えたのだった。
このことがあってしばらくして、私は中学三年生となり、進学か就職か、進路選択を迫られるようになった。私としては、勿論進学したいのはやまやまであったが、我が家の経済状況を思えば、就職の道を選ぶより外はなかった。
「女も手に職を持たせにゃいけん。長え一生にゃ、何があるか分からんけんなあ」
という母の言葉に従って、私は、美容師になることに決めた。
母にしてみれば、今までの自分の人生を振り返って、父が突然、失明した時でも自分に手に職があったなら、何も女だてらに道路人夫に混じって、暑い夏にはジリジリと照りつける日の下で、また冬には、身をきるような木枯らしにさらされながら、小雪の降る中を、男衆がツルハシで彫り返した土や石をリヤカーに積んで運んだりするような、激しい肉体労働もしなくてすんだ筈であった。そんな思いを込めた言葉であったと後に母から聞いたが、そのころの私には、そこまで思いを巡らす事は出来なかった。
しかし、あんなに反抗していた母の言葉に素直に従う気になったのは、きっと母が初めてパーマネントをかけたあの日のことが、私の心の奥深くに残っていたからだと思うのである。
(福岡県北九州市)
【無断転載を禁ず】
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会 文化財・生涯学習課
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
お問い合わせはこちらから

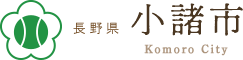


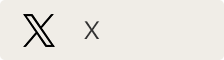


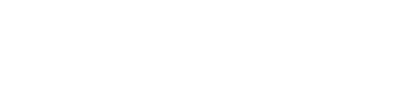

更新日:2019年03月28日