生活保護制度について
1.生活保護とは
病気や失業などにより、生活に困っている人に対し、状況により必要な援助を行うとともに、自立のお手伝いをする制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。生活が苦しく、自力ではどうにもならないと感じたら、ためらわずにご相談ください。
2.生活保護の基本原理
| 国家責任の原理 | 国の責任において行われます。 |
| 無差別平等の原理 | 要件にあてはまればどなたにでも行われます。 |
| 最低生活保障の原理 | 健康で文化的な最低生活を保障します。 |
| 補足性の原理 | 利用出来る全ての資産・能力その他あらゆるものを活用しても、足りない部分を援助します。 |
3.生活保護のしくみ
1)保護の要否決定
最低生活費と世帯の収入を比較し、保護が必要か判断します。
- 最低生活費:国が定めた生活保護に関する基準。世帯員の年齢や人数、必要な医療費や障害の程度等により算出されるため、各世帯ごとに違います。
- 世帯の収入:世帯全員の働いた収入、各種年金・手当、親族等からの仕送り、預貯金、保険金、財産を処分して得た収入など
※最低生活費には借金やローンの返済は含まれていません:生活保護はあくまで最低限度の生活の保障を行う制度のため、借金やローンの返済などは原則認められません。そのため、生活保護を受給する場合は、法テラス等を利用して自己破産の手続きを進めたり、多額のローンが残っている住宅に居住していたり、車等の財産を所有している場合はその処分を行ない、生活費に充当する必要があります。
保護費の支給基準
保護の要否決定により、下図左のとおり収入が最低生活費に満たない場合、生活費の不足している部分が保護費として支給されます。

2)保護の種類
生活保護には飲食、衣服、光熱費など日常生活に必要な費用を援助する生活扶助の他に、医療扶助、住宅扶助など8種の扶助があり、最低限度の生活に足りない分について援助が行われます。
| 生活扶助 | 衣食その他の日常生活に必要な費用 |
| 住宅扶助 | 家賃、地代、住宅補修に必要な費用 |
| 教育扶助 | 義務教育に伴う学用品や、給食費などの費用 |
| 医療扶助 | 病気やけがの治療、処方箋、医療用具などの費用 |
| 介護扶助 | 介護保険の在宅、施設サービス利用に必要な費用 |
| 出産扶助 | 出産に必要な費用 |
| 生業扶助 | 技能習得、高等学校就学に必要な費用 |
| 葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
4.生活保護を受けるには
家族全員の
- 働く能力
- 資産(預貯金・保険・不動産等) ※居住用以外の資産(車や保険など)は原則すべて処分(解約)が必要
- 親族(親・子・兄弟等)からの援助 ※ 親・子・兄弟は民法で絶対扶養義務者とされています
- 他の法律による給付(各種年金・手当等を全て受ける事。)
など、あらゆる事を行っても最低生活ができない場合。原則、家族(世帯)を単位として生活保護が適用されます。
- 申請は、保護を受けようとする本人または、その人と生計を同一にする家族が行うことができます。
まずは福祉事務所(市役所厚生課)へご相談下さい。
5.生活保護の権利と義務
権利
- 正当な理由がないのに、保護費を減らされたり、保護を止められたりすることはありません。
- 生活保護で受けた現金や品物を差し押さえられることはありません。
- 生活保護で受けた現金には税金がかかりません。
義務
- 働ける人はその能力に応じて働かなければなりません。病気により働けない人は医師の指示に従って治療に専念しなければなりません。また、日常生活においては自らの健康維持に努め、支給された保護費は節約し、計画的に使わなければなりません。
- 収入や支出などの家計、住まいや家族構成、医療機関の受診や入院、退院、就職や転職、退職等、世帯の状況に変更があるときは速やかに福祉事務所へ届け出てください。
- 生活の維持向上又は義務を怠ったとき、その他保護の目的を達成するために必要があると認められるときは、福祉事務所が指導や指示を行います。その際は必ずそれに従ってください。正当な理由がなく、指示や指導に従わないときは保護の変更、停止または廃止になる場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保健福祉部 福祉課 保護社会係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966
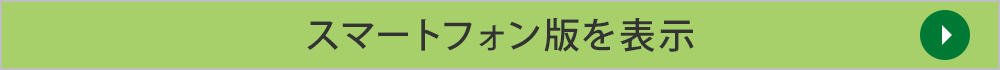
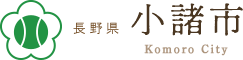
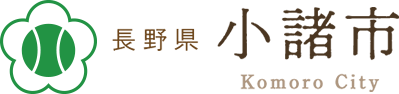

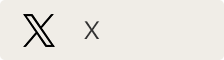


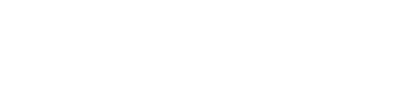

更新日:2023年07月21日