令和8年度から適用される市・県民税(個人住民税)の主な税制改正
令和8年度以降に適用される市・県民税(個人住民税)の主な改正事項をお知らせします。
なお、税制改正の詳しい内容につきましては下記リンク先をご確認ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁ホームページ)
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市県民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます
|
給与等の収入金額 |
改正前給与所得控除額 |
改正後給与所得控除額 |
||
|---|---|---|---|---|
|
1,625,000円以下 |
550,000円 |
650,000円 |
||
|
1,625,000円超 1,800,000円以下 |
給与等の収入金額×40%ー100,000円 |
650,000円 |
||
|
1,800,000円超 1,900,000円以下 |
給与等の収入金額×30%+80,000円 |
650,000円 |
||
|
1,900,000円超 3,600,000円以下 |
給与等の収入金額×30%+80,000円 |
改正なし |
||
|
3,600,000円超 6,600,000円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万円 |
改正なし |
||
|
6,600,000円超 8,500,000円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 |
改正なし |
||
|
8,500,000円超 |
195万円 |
改正なし |
||
給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第5(外部リンク)によって求めた金額となります。
各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引き上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市県民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
|
扶養親族の区分 |
改正前 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
改正後 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
|---|---|---|
|
扶養親族 |
48万円以下(103万円以下) |
58万円以下(123万円以下) |
|
同一生計配偶者 |
48万円以下(103万円以下) |
58万円以下(123万円以下) |
|
ひとり親の生計を一にする子 |
48万円以下(103万円以下) |
58万円以下(123万円以下) |
|
配偶者特別控除の対象になる配偶者 |
48万円超133万円以下 |
58万円超133万円以下 |
特定親族特別控除の創設
納税義務者が特定親族(19歳以上23歳未満)を有する場合には、その納税義務者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されます。
なお、一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。
| 特定扶養の合計所得金額 (給与収入ベース※) |
控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
※給与収入ベースは、判定の対象となる所得が給与所得のみ場合の給与収入金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。
勤労学生控除適用の所得要件の緩和
勤労学生控除を適用するための所得要件が、合計所得75万円以下から85万円以下に緩和されます。
家内労働者等の特例による控除額の引き上げ
家内労働者等の特例の適用により、収入から差し引かれる控除額が最大55万円から最大65万円に引き上げられます。
令和6年度から適用される市・県民税(個人住民税)の主な税制改正
以下は令和6年度から適用された主な税制改正になります。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
令和5年分以降の所得について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することはできません。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
2.障害者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
提出または提示が必要な書類
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市県民税税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。
ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
- 留学ビザ等書類
2.障害者
- 障害者手帳等
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
- 38万円以上の送金書類
森林環境税の創設
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
令和6年度から、個人の市・県民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、市・県民税と合わせて小諸市が徴収します。
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
| 税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
|---|---|---|
| 森林環境税 | ー | 1,000円 |
| 県民税 均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
| 市民税 均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
| 合計 | 5,500円 | 5,500円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
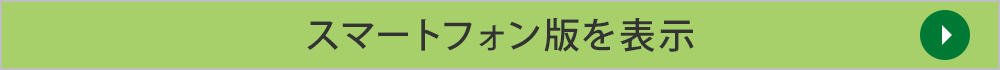
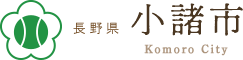
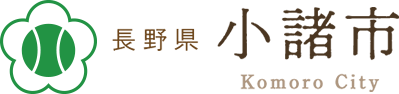

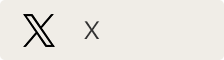


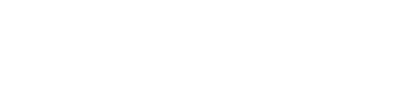

更新日:2025年10月23日