児童手当制度の改正について(令和6年10月分以降)
令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当制度が改正されます。
1.制度改正の内容
1.所得制限の撤廃
2.支給対象年齢が「中学生」から「高校生年代」までに延長
3.第3子以降(多子加算)の手当額を月額15,000円から30,000円に増額
4.第3子以降(多子加算)の算定対象を「高校生年代」から「大学生年代」に延長
5.支給月を年6回に変更
|
|
改正前 |
改正後 |
|
所得制限 |
所得制限、上限限度額あり |
所得制限なし |
|
支給対象 |
中学生まで (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
|
手当額 (月額) |
・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ※所得が所得制限以上の場合は特例給付として児童一律5,000円 |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
|
第3子以降の算定対象 |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
大学生年代まで ※ (22歳到達後の最初の3月31日まで) |
|
支給月 |
6月、10月、2月(年3回) 各前月までの4か月分 |
偶数月(年6回) 各前月までの2か月分 |
※大学生年代の子においては進学・就職等に関わらず親等の経済的負担がある場合(経済的負担とは、子が受給者の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。)食費や家賃、学費等のほか、金銭以外の仕送り(食料品や生活必需品等)も含まれます。子が独立して生計を営んでいる場合は算定対象外です。
【例】大学生(21歳)、中学生(14歳)、小学生(7歳)を養育している場合
大学生を第1子、中学生を第2子、小学生を第3子とカウントします。
中学生は月額10,000円(第2子)、小学生は月額30,000円(第3子)となります。
2.制度改正による申請が必要な方
申請が必要と思われる方には、9月上旬に通知及び申請書を送付しますので、確認の上、ご提出をお願いいたします。
なお、住民票が申請者と別世帯または市外の児童は市で把握できず、通知が届かない場合もあります。
その他、申請が必要な方で通知が届かない場合は市へお問い合わせの上、申請をお願いいたします。
(注意事項)
※公務員の場合は職場から児童手当が支給されるため、勤務先へ申請してください。
※単身赴任等により所得が高い方の住民票が市外にある場合は、住民票がある市区町村へ申請してください。
新たに受給資格が生じる方
- 所得上限限度額以上により、資格喪失となっている方
- 高校生年代の児童のみ養育している方
提出書類
- 【必須】認定請求書
認定請求書(PDFファイル:172.6KB)
(記入例)認定請求書(PDFファイル:245.4KB) - 【必須】請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
- 【該当の方のみ】監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代の子を算定対象に含める場合は提出してください。
養育している子が大学生年代の子を含めて3人以上の場合・・・多子加算の対象のため、必要
養育している方が大学生年代の子を含めて2人以下の場合・・・多子加算の対象外のため、不要
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:92.6KB)
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:137.7KB) - 【該当の方のみ】別居監護申立書
高校生年代までの子について、住民票上別居しているが養育している場合は提出してください。
別居監護申立書(PDFファイル:48.2KB)
(記入例)別居監護申立書(PDFファイル:280.5KB)
受給額が増額する方
- 児童手当受給中で、算定対象として認定されていない高校生年代の児童がいる方
- 児童手当受給中で、新たに多子加算の算定対象となる大学生年代(18歳年度末経過後、22歳年度末まで)の子がいる方
※大学生年代の子を含めて、養育する子が3人以上の場合、多子加算の対象のため申請が必要
大学生年代の子を含めても、養育する子が2人以下の場合、多子加算の対象外のため申請は不要
提出書類
- 【必須】額改定届
額改定届(PDFファイル:81KB)
(記入例)額改定届(PDFファイル:304.4KB) - 【必須】請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
- 【2の方】監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:92.6KB)
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:137.7KB)
申請方法・申請期限
【窓口】こども家庭支援課(平日8:30~17:15)
【郵送】同封の返信用封筒をお使いください。
☆窓口混雑回避のため、郵送による申請にご協力をお願いいたします。
申請期限:令和6年10月31日(木曜)
制度改正後の初回支給(令和6年12月支給)に反映させるため、期限までの申請にご協力をお願いいたします。
※令和7年3月31日(月曜)までに申請いただければ、令和6年10月分から遡って支給します。
3.制度改正による申請が不要の方
手当額が変わる方については、令和6年10月以降に通知を送付します。
- 児童手当受給中で、制度改正後も支給額が変わらない方
- 児童手当受給中(特例給付)の方
(令和6年10月分以降は特例給付から改正後の手当額になります) - 児童手当受給中で、算定対象として認定されている高校生年代の児童がいる方
(令和6年10月分以降は算定対象から支給対象になります) - 現行でも多子加算を受けている方
(例:4歳の児童(第3子)がいる場合、15,000円→30,000円になります) - 新たに多子加算を受ける方
(例:3歳未満の児童(第3子)がいる場合、15,000円→30,000円になります)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保健福祉部こども家庭支援課こども保育係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
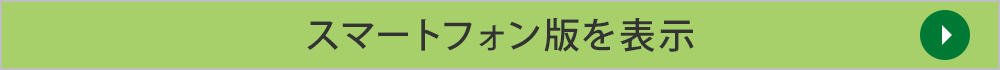
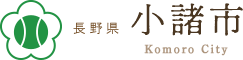
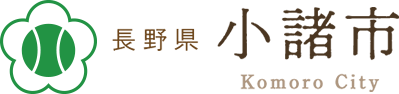

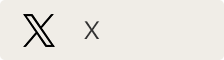


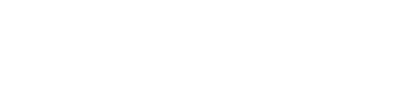

更新日:2024年12月12日