長期学校改築計画に関する市民学習会を開催しました(平成28年5月)
10月5日午後7時から、市民交流センターのステラホールで「長期学校改築計画に関する市民学習会」を開催しました。
今回の学習会は、去る5月14日の「学校改築市民懇話会」でいただいた意見をもとに、次の2点をテーマとして開催したもので、あいにくの雨模様の天候にもかかわらず約100名の皆様にご参加いただきました。
- 基本的なデータによる情報の共有
あらためて市民の皆様と行政とが共通の認識に立つために、
データに基づいて基本的な状況を確認・共有する。 - 『たたき台』をつくり、実効ある議論を進めるための方法
長期学校改築計画策定の進め方について、市民の皆様からご意見を伺う。
学習会では、まず、教育委員会事務局から「学校施設の現状」「児童・生徒数の見込み」「学校改築費用の試算」など学校改築に関するデータを、また、財政課から「小諸市の財政状況」についてのデータをお示ししました。
その後、参加した皆様と意見交換を行い、次のような基本的な方向性についてご賛同をいただきました。
- 計画の『たたき台』をつくるために、検討組織を設置する。
- 検討状況について、市民の皆様へお知らせする。
- 検討組織と市民の皆様との意見交換の場などを設ける。
今後は、学習会でいただいたご意見を踏まえて、教育委員会として具体的な進め方を決定し、計画策定に取り組んでいきます。
引き続き、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

いただいたご意見ご質問と回答
項目
早期検討
参加者の皆様からのご意見・ご質問
- 小学校は、建設から既に40年から50年が経過している。今後さらに30年、40年ともたせることができるのか。早い決断が必要である。
事務局の回答等
- これまでの事例からすると、1校の建替えには数年かかるものと考えられます。小諸市の財政状況では同時に複数校を改築することは困難です。建替えには相当な期間を要しますので、できるだけ早く計画を策定したいと考えています。
項目
検討組織
参加者の皆様からのご意見・ご質問
- 検討組織による議論を進めて欲しい。
- 検討組織の議論を市民が共有できるような配慮をしてほしい。
事務局の回答等
- 計画の策定は、効率的に進めることとともに、できるだけ市民の皆様のご意見をお聴きし、反映させることが必要だと考えています。そのためには、まず検討組織を設置し、そこでの議論の中から『たたき台』をつくり、それを市民の皆様にお示しし、市民の皆様のご意見をお聴きしながら再度検討する。そういった仕組みを構築し、スピード感を持って進めていきたいと考えています。
- 検討組織は、今後の教育のあり方はもちろん、地域コミュニティ、まちづくりなどに知見を有する方をはじめ、保護者、学校関係者、地域住民、公募市民などで構成し、議論をいただいたらどうかと考えています。なお、限られたメンバーだけの議論にならないよう、検討組織と市民の皆様とが意見交換をする場を設けるなどのプロセスを経て、方向を見出していってはどうかと考えています。
項目
長寿命化
参加者の皆様からのご意見・ご質問
- コンクリートが劣化していても長寿命化改修はできるのか。
事務局の回答等
- 長寿命化改修をするためには、コンクリートの状況を調査する必要があり、調査結果によっては、長寿命化改修が難しい部分もあるのではないかと思われます。
参加者の皆様からのご意見・ご質問
- 40年経ったから建て直さないといけないという考え方は捨てるべきである。長寿命化を考えながら、改築計画を進めて欲しい。
事務局の回答等
- 長寿命化と改築を組み合わせて考えていく必要があると考えています。
項目
複合化
参加者の皆様からのご意見・ご質問
- 計画策定にあたり、防災の拠点、地域のコミュニティの場としての観点は考慮するのか。
事務局の回答等
- 学校は、災害時には避難場所になるほか、コミュニティスクールの取組みなど、地域との関わりが深く、計画策定にあたっては、学校が持つこうした多様な機能を考慮すべきと考えています。
参加者の皆様からのご意見・ご質問
- 学校の機能だけにとらわれず、広い視野で考えたらどうか。福祉施設や保育園等と複合化して、世代間交流や地域の人々とのふれあいができる場とするなどの柔軟な考え方も必要ではないか。
事務局の回答等
- 学校のあり方について考える場合、一番に据えるべきは子どもたちです。検討する際は、幅広いご意見を伺いたいと思います。
項目
小中一貫
参加者の皆様からのご意見・ご質問
- 小中一貫校の方針をとるのかどうかを考えてから、計画策定を進めてはどうか。
事務局の回答等
- 小中一貫校の取組みは、まだ始まったばかりであり、教育的にどのような効果があるか見極めが必要です。なお、児童・生徒数が減るから小・中学校をまとめるという考え方ではなく、子どもたちにとってどういう教育環境が望ましいのかという観点から議論を進める必要があると考えています。
- この記事に関するお問い合わせ先
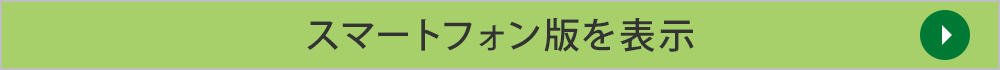
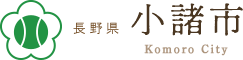
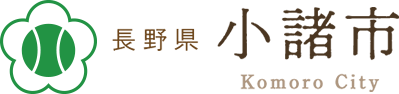

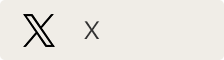


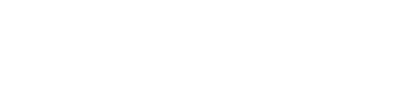

更新日:2021年12月27日