後期高齢者医療制度のしくみと保険給付
後期高齢者医療制度の運営について
運営主体
長野県内のすべての市町村が加入する「長野県後期高齢者広域連合」が運営を行います。
〔長野市大字中御所字岡田79-5 NOSAI長野会館 電話026-229-5320〕
広域連合の役割
- 制度の運営
- 被保険者の資格管理
- 保険料の決定
- 給付に関する決定
市町村の役割
- 各種証書の引渡し
- 保険料の徴収
- 医療給付に関する申請の受付 など
ホームページ
その他、詳細等につきましては、下記アドレスから長野県後期高齢者広域連合ホームページをご覧ください。
対象になる方について
75歳以上の方
75歳の誕生日当日からの加入となります。加入手続きは不要です。
65歳から74歳までの方で、一定程度の障がいがあり、加入を希望する方(任意加入)
申請により後期高齢者医療に加入することができます。
※75歳になるまでは、いつでも加入や撤回ができます。ただし、加入や撤回を申請日よりさかのぼってすることはできません。
保険証について
令和6年12月2日に、従来の保険証の新規発行、再発行は終了しました。
マイナ保険証について
健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を医療機関や薬局に設置されたカードリーダーにかざすだけで、最新の資格情報が確認できます(オンライン資格確認)。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
資格確認書について
令和8年7月末まで、マイナ保険証をお持ちであるかどうかにかかわらず、資格確認書を交付します。
資格確認書を医療機関等に提示することで、保険証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができます。
75歳の誕生日を迎える方(新しく後期高齢者医療に加入する方)
誕生日の前月下旬に資格確認書を送付します。
※令和8年7月末まで、マイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書を送付します。
医療機関窓口での自己負担割合について
自己負担割合
|
所得区分 |
自己負担割合(外来・入院) |
判定基準 |
|---|---|---|
|
現役並み所得者 |
3割 |
世帯内に住民税の課税標準額が145万円以上あるこの医療制度の被保険者がいる方。 ただし、世帯の収入の合計が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合、申請により1割または2割負担となります。 |
| 一般II | 2割 |
現役並み所得者、住民税非課税世帯以外の被保険者及び同一世帯の被保険者で、 ・被保険者が1人の世帯 「住民税課税標準額28万円以上」、かつ「年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上」 ・被保険者が2人以上の世帯 被保険者のうち、「住民税課税標準額28万円以上の方がいる」、かつ「被保険者全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上」 |
|
一般I |
1割 |
現役並み所得者、一般II、低所得者1・2のいずれにもあてはまらない方。 |
|
低所得者II(区分II) |
1割 |
同一世帯の全員が住民税非課税である方 (低所得者1以外の方)。 |
|
低所得者I (区分I) |
1割 |
同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。 |
入院したときの食事代などについて
低所得I・II(区分I・II)の方は、オンライン資格確認、又は所得区分の記載された資格確認書を医療機関に提示することで、所得区分が確認され、入院中の食事代が減額されます。
※ 資格確認書に所得区分の記載がない方は、市役所で「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」の申請が必要です。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
|
所得区分 |
1食あたりの食費 |
|---|---|
|
現役並み所得者 及び一般 |
510円 ※1 (490円) |
|
低所得者II (区分II) |
240円 (230円)
◎過去12か月で90日を超える入院の場合※2 190円(180円) |
|
低所得者I(区分I) |
110円 |
令和7年3月31日までは( )内金額が適用となります。
※1 指定難病の方は、300円です。
※2 適用を受ける場合は窓口で長期入院該当の申請をしてください。
長期入院該当は、申請日の翌月1日から有効となり、申請日から月末までは差額
支給の対象となります。
療養病床に入院した場合の標準負担額
|
所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
|---|---|---|
|
現役並み所得者及び 一般I・II |
※1生活療養費I 510円※3(490円) ※1生活療養費II 470円※3(450円) |
370円※4 |
|
低所得者II |
240円(230円) ◎90日を超える入院の場合※2 240円(230円) |
370円※4 |
|
低所得者I |
140円 ◎老齢福祉年金受給者または境界層該当者 |
370円※4 ◎老齢福祉年金受給者または境界層該当者 |
令和7年3月31日までは( )内金額が適用となります。
※1 医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
※2 診療報酬の内容によって金額が異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
※3指定難病患者の方は、300円
※4指定難病患者の方は、0円
高額療養費について
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。該当した場合は、申請のお知らせをします。申請は初回のみ必要で、それ以降は申請口座に自動的に振込となります。
なお、支給対象になるものは、保険適用部分のみで、食事代、ベッド代の差額等は対象外となります。
自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 個人(外来のみ) | 世帯(外来と入院を合算) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者III |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【多数回140,100円 ※2】 |
|
| 現役並み所得者II※1 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【多数回 93,000円 ※2】 |
|
| 現役並み所得者I ※1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【多数回 44,400円 ※2】 |
|
| 一般 |
18,000円 【年間上限額144,000円 ※2】 |
57,600円 【多数回 44,400円 ※2】 |
| 低所得者II ※1(区分II) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者I※1(区分I) | 8,000円 | 15,000円 |
- ※1 1か月(同じ月内)の医療費が高額になる入院等のときに、オンライン資格確認、又は所得区分が記載された資格確認書を医療機関へ提示することで、窓口での自己負担額が減額されます。
- ※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
75歳の誕生月の自己負担限度額の特例
月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方は個人単位の自己負担額は、75歳の誕生月に限り2分の1になります。ただし、1日生まれの方、障がい認定(任意加入)の方は特例はありません。
高額介護合算療養費について
1年間(8月から翌7月分までの期間)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の自己負担分を合算し、限度額を超えた分(支給基準額が500円を超えた場合に限る。)が申請に基づき支払われます。
特定疾病について
- 厚生労働大臣が定める特定疾病の場合、1か月(同じ月内)に同じ医療機関等での自己負担限度額(月額)は、入院・外来それぞれ10,000円となります。
- この場合では「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、市民課国保年金係の窓口で申請してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
医療費の払い戻しを受けられる場合について
次のような場合は、医療費はいったん全額自己負担になりますが、市民課国保年金係の窓口で申請し、長野県後期高齢者医療広域連合で認められれば、自己負担分を除いた額があとから療養費として支給されます。
医療費の払い戻しについて
|
どんなとき? |
申請に必要なもの |
|---|---|
|
やむを得ない事情で10割負担で受診したとき |
領収書、印鑑、医療機関が発行する診療報酬明細書 |
|
コルセットなど治療に必要な補装具を購入したとき |
領収書、印鑑、医師の診断書または意見書 |
|
保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
領収書、印鑑、施術明細書(医師の同意書が必要な場合があります) |
|
医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージの施術を受けたとき |
領収書、印鑑、医師の診断書または同意書 |
|
海外渡航中に病気やけがのため診療を受けたとき(受診目的の渡航はのぞく) |
領収書、印鑑、海外の病院が発行する診療明細書(日本語の翻訳文を添付) |
その他の給付
次のような場合にも市民課国保年金係の窓口で申請することによって給付を受けることができます。
- 移送費がかかったとき(医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったときは、申請して長野県後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合は移送費が支給されます。)
・ 申請時に必要なもの
資格確認書、印鑑、通帳、領収書、移送を必要とする医師の意見書
第三者行為について
交通事故などにあったとき
交通事故など、第三者(加害者)の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。
- 警察に届け出て、「事故証明書」をもらいましょう。
- 必ず市民課国保年金係の窓口で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
・ 申請時に必要なもの
資格確認書、印鑑、事故証明書(後日でも可)
※ご注意ください!
先に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療で医療を 受けることができなくなることがあります。示談の前に必ず市民課国保年金係でご相談ください。
葬祭費について
被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った人が市民課国保年金係の窓口で申請し、長野県後期高齢者医療広域連合で認められれば、50,000円の葬祭費が支給されます。
・ 申請時に必要なもの
資格確認書、印鑑、通帳
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課 国保年金係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
お問い合わせはこちらから
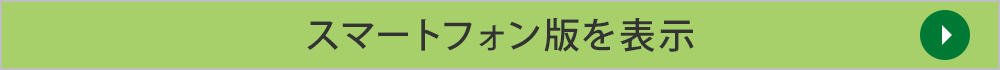
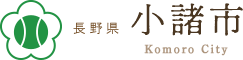
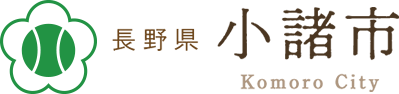

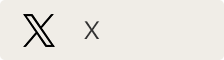


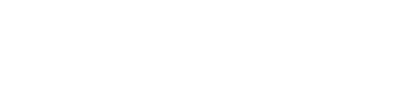

更新日:2025年08月01日