東山道清水駅跡
とうさんどうしみずうまやあと 東山道清水駅跡
| 指定項目 | 東山道清水駅跡 |
|---|---|
| 所在地 | 小諸市諸 |
| 所有者及び管理者 | 清水駅跡保存会 |
| 指定年月日 | 昭和46年3月31日(史跡) 指定番号 4-3 |
概説
東山道は、山陽道・山陰道・東海道・北陸道・南海道・西海道と並ぶ古代の官道の一つで、その成立は律令制度が整備された7世紀以降と考えられている。こうした官道には、30里(約16キロ)ごとに駅が置かれ、清水の駅も信濃にある15の駅の一つである。
官道や駅の制度は大和朝廷が政治上の目的をもって設置した機関・制度であることから、中央の役人の往来や軍事のためのものであった。
駅に駅長が置かれ、10疋の駅馬を常備していたほか、佐久郡で5疋の伝馬(駅馬とは別に置かれ、公開旅行の役人に使わせた)を置くなどの規則が設けられていた。
水の確保もその条件の一つであり、水の豊富な諸はうってつけであったと言えるかもしれない。この清水の駅は全長約270メートルあり、中央の道路をはさんで両側に、間口およ22メートル、奥行およそ45メートルの地割をして駅の役人たちの屋敷にし、道路の中央には駒飼の堰を通し、また屋敷北側の後ろには飲堰を流し、それに沿って俗に夜盗道という小道が通じている。この堰は、駅跡の両端でさらに南へ枝堰を分ち、中央の道を過ぎ南側にのび、南側の地割の後ろにも堰の跡が認められる。
このように、道、地割、堰を残していることから、駅制など古代の交通制度研究の上で貴重な遺跡である。

- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会 文化財・生涯学習課
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
お問い合わせはこちらから
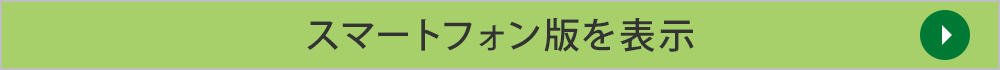
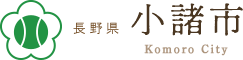
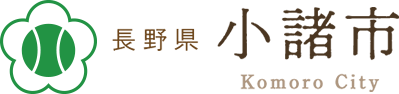

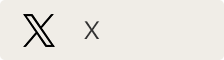


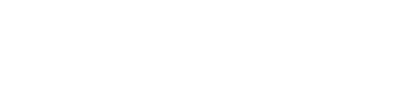

更新日:2019年03月28日