医療の給付
医療機関で国民健康保険の資格確認書またはマイナ保険証を提示すれば、診察、治療、入院、薬などにかかる医療費について、次の区分による一部負担金を支払うことで、残りは国民健康保険から支払われます。ただし、差額ベッド代や正常な妊娠、出産など保険適用されないものもあります。
自己負担割合
小学校就学前
2割
小学校就学後から69歳
3割
70歳以上 75歳未満
- 2割
- 現役並み所得者は3割
※現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上の方とその同一世帯の方。基準等について、詳しくはお問い合せください。 - 医療機関等の受診時に、請求額について疑問に思われた場合(お持ちの資格情報書類と異なる窓口負担割合で請求された場合など)はご相談ください。
医療費を全額支払ったとき
次のような理由で医療費を全額支払ったときは、申請により国民健康保険負担分の医療費について給付を受けることができます。
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
- 海外で診療を受けたとき
- 急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関にマイナ保険証または資格確認書を提示できなかったとき
※理由により申請に必要な書類等が異なります。詳しくはお問い合せください。
その他の給付
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときに、出産育児一時金として、出生児1人につき50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8,000円)が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産、流産でも支給されます。
※会社を退職後6か月位以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます(ただし、一年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。
出産育児一時金の直接支払制度
出産に要する費用の経済的負担を軽減し、安心して出産できるよう国民健康保険から出産育児一時金の額を上限として、出産費用を直接医療機関へ支払う「直接支払制度」が導入されました。
1.直接支払制度を利用する場合
出産の際に、分べん機関等でマイナ保険証もしくは資格確認書を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面(合意文書)で取り交わしてください。
出産費用が出産育児一時金を上回る場合
国民健康保険から出産育児一時金の全額が分べん機関等へ支払われます。
出産育児一時金との差額を医療機関等へお支払いください。
出産費用が出産育児一時金を下回る場合
国民健康保険から出産費用(実費)が医療機関等へ支払われます。
出産育児一時金との差額は、医療機関等から交付された領収・明細書(写し)を添付し、市民課・国保年金係に申請をしてください。
2.直接支払制度を利用しない・できない場合
直接支払制度を利用しない場合または海外での出産や医療機関等の都合上、直接支払制度を利用できない場合は、出産費用の全額を一旦医療機関等にお支払いいただき、領収・明細書等の写し及び合意文書(直接支払制度を利用しない旨の合意)の写しを添付し、市民課・国保年金係へ申請をしてください。
申請に必要なもの(日本国内での出産の場合)
- マイナンバーカード
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 印鑑(認印)
- 預金通帳など振込口座のわかるもの
- 出産費用の内訳を記した領収・明細書(産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産の場合は指定の証明印が押されたもの)
- 医療機関等から交付される合意文書
申請に必要なもの(海外での出産の場合)
出産日に小諸市の国民健康保険に加入している方が海外で出産した場合に、帰国後市役所窓口にて支給申請することにより出産育児一時金が支給となります。
- マイナンバーカード
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 印鑑(認印)
- 貯金通帳など振込口座のわかるもの
- 出産費用の領収書及び診療明細の写しとその和訳分(翻訳者名を記入)
- 海外へ出入国したことが確認できる書類(パスポートの写し等) ※1
- 出産の公的証明(戸籍等)
- 現地の医療機関等に対して照会を行うことへの同意
※1出入国スタンプが押されていない場合は、搭乗券の半券等渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
※申請期限は出産日翌日から2年間です。
海外出産に係る出産育児一時金の支給適正化に向けた対策について
平成31年4月1日付(一部改正:令和5年5月24日)厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しております。国内に住民票を有しているものの実際には海外に長期間滞在する方が、海外出産に係る出産育児一時金の支給申請を行った場合には、その方が小諸市に生活の拠点を有し、かつ、国民健康保険の被保険者資格を有する方であるかについて住民基本台帳担当と連携し、適正に審査を行います。
また、不正請求が疑われる場合には警察とも相談・連携し厳正な対応を図ります。
適正化対策の趣旨を理解いただき、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行う方に50,000円が支給されます。
死亡手続きの際に申請をしていただきます。
交通事故にあった場合
交通事故など、相手方(第三者)の行為によってけがや病気をした場合の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、状況によって国保で診療を受けることができます。その場合は、必ず市民課・国保年金係に連絡し、下記の「第三者行為による傷病届」等を提出してください。
- 先に相手方から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、国保で診療を受けることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
届出に必要なもの
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・念書
・警察が発行する交通事故証明書
・交通事故証明書入手不能理由書(交通事故扱いでない場合に必要)
・誓約書(相手方が記入)
・同意書
・マイナンバーカード
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・認印
・第三者行為による傷病届 (Excelファイル: 91.0KB)
・事故発生状況報告書 (Excelファイル: 48.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課 国保年金係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
お問い合わせはこちらから
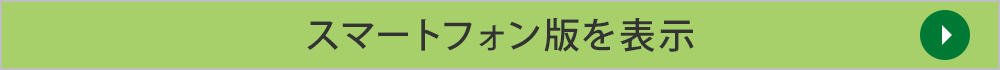
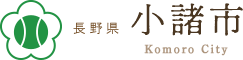
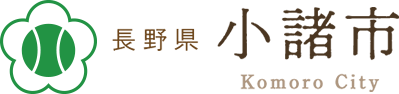

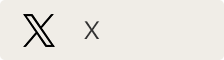


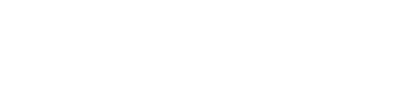

更新日:2019年08月16日