第3回市民懇談会
平成23年12月16日に行われた第3回市民懇談会のまとめです。
第3回は、第2回目までにまとめた懇談会の意見・要望がどうプロポーザルや市の施策に反映されたかの「報告会」という形で行われました。
| 市民からの意見・要望 | 建設室・図書館からの回答 |
|---|---|
| あいおい公園の場所は決定しているのか?あいおい公園の中で向きを変え、まちなか多目的施設の位置を変えることができれば、図書館をもう少し相生町通りに面して出せるのでは? | 建設室:都市計画決定されているので、あいおい公園の場所・施設の位置等の変更は難しいと思われる。プロポーザルで、専門家の視点で施設の配置等様々な提案があると思われるので、期待したい。 |
| 仮設の期間は最短と最長で、どれくらいになるのか? | 建設室:市庁舎敷地内に建設するとしたら、建設場所によるが、最短で2年半くらい。長くて3~4年になると思われる。 |
| 児童書・一般書は同じ場所の方がいいのか?児童書はこもロッジ等に置く事はできないか? | 図書館:現在の利用をみると、土日など家族で来て子どもの絵本と親の一般書などを一緒に借りている。分散して施設が離れていると使い勝手が悪いのではないかと思われる。出来れば、同じ建物にしたいと考えている。 |
| 仮設引越しのよその事例はないのか? | 図書館:調べてみたが、いったん仮設に移ってから新設の図書館に、という事例はないようだ。 |
| この小諸図書館が出来た際も、貸出しがなく閲覧のみだった期間があったように思う。 | 図書館:現在でも、全く貸出しの出来ない閉館期間は必要だと考えている。 |
| この現図書館はいつまで今の状態でおいておけるのか?新図書館が出来てから引越しではだめなのか? |
建設室:市民会館と一緒に解体するとして、一番最後に解体するとしても、現在のスケジュールでは11月末までには解体することになる。 現図書館からそのまま新図書館に行けるほうが、職員の負担は少ないが、今までの懇談会の中でも、周辺の工事状況による利用者の皆さんの安全や、雨漏りなどの図書館の現状を考え、仮設に移転することが望ましいというまとめに至っている。 |
|
引越しは機能分散を考える良い機会である。この機会に蔵書の整理を進めて機能を分散させれば、仮設図書館の面積も少なくてすむ。 古文書等を別の場所に持っていけば、研究施設としての使い方も考えられるのではないか。 |
建設室:古文書・和漢書を別の施設に 移し、研究をしていただくのも良いか もしれない。 図書館:分散すればそれだけ人も必要 になるし、職員の負担も増える。 確かにこの図書館は、いろいろなものがありすぎて、どれが貴重でどれが貴重でないのか不明なものもある。研究資料もすべてを図書館で扱うべきかを検討する良いきっかけかもしれない。図書館のあり方を考えるのにも良い機会だと思って、出来る限り考えていきたい。 建設室:仮設の設置については、必要面積・必要冊数などと共に、建設するのか、既存施設を使うのか、いろいろな方法を検討している。 利用者の声を聞きたい。参考にさせていただき、教育委員会としての方向性を出していきたいと考えている。 |
| 建てるなら泉万跡地にプレハブが良いと思う。既存の施設を借りるならJA東信会館で、利用頻度の低いものをNTTビルに置いてはどうか?JA東信会館は使いづらいのではないかということだが、そこなら近くに小中学校もあるし、商業施設もあるので良いと思う。 | 建設室:現図書館から近い場所、中高生が使える場所ということから市街地が望ましいと考えている。JA東信会館も検討した。場所がそこで良いのかということ。中高生が行きにくいことが問題だと考えている。中高生の1年は我々大人の1年とは違う。なるべく図書館を開けたいと考えている。また、仮設であっても、中高生のための勉強スペースはとりたいと考えている。限られたスペースにあれもこれもと入れることはできない。職員のためのスペースやボランティアのための作業スペースも確保したいという声もある。限られたスペースの中では利用者を優先したいと建設室は考える。 |
| 館長はどう考えているのか? |
図書館:出来る限り市街地で、十分な面積をとって建ててほしい。それにはお金がかかる。 可能な限り利用者にもいい環境で利用していただきたいし、職員にもいい環境で働いてもらいたいと考えている。 建設室とすり合わせをしていく中で、ゆずれる面はゆずっていく。一番は利用者が安全に借りに来てもらえること。 |
|
後利用が可能なものにしたらどうか? お金がかかっても、その後使えれば良いのではないか。 まずは2~3年を安全に利用できればいいのではないか。既存の施設は難しいように思う。 |
建設室:建設かリースか既存施設を使うかは費用対効果の問題になってくる。後利用ということであれば、施設としての目的を持たなければならないし、後の管理・維持費のことも考えなければならない。 どちらにしても建てるのであれば、市街地でもあるし、前回から提案いただいている泉万跡地も魅力的である。 |
| 泉万跡地に駐車場はあるのか? | 建設室:建物を何にすればいいのか、それによって駐車場の面積も変わってくる。 |
| 駐車場は新しい図書館にも付いてくる問題。利用する人のモラルの問題だと思う。 | |
| ICタグはどうしていくのか? |
図書館:今検討しているところ。 駅舎併設案の際には消極的だったが、当時とは状況が変わってきている。当時は盗難防止が中心だったが、今は利用者のプライバシーの観点から必要ではないかと考えている。 建設室:駅舎併設案の際は、セキュリティゲートの雰囲気がいや、という意見があった。その後いくつかの施設に視察に行ったが、皆違和感なく使っていた。 個人情報の保護はこれからの重要な課題。安曇野市中央図書館では、年配の方も自動貸出機を使っていた。利用者もほとんどが自動貸出機を使っている。導入は検討してみたい。 他の方はどうか? |
| こちらがゲートや自動貸出機に慣れていかないといけないと思う。 | |
| 東京の図書館を利用しているが、自動貸出機は(職員の目を気にせずに)好きな本を借りられるし、とても面白いと思って使っている。 | |
|
新しく造るのであれば、名所になるくらいすごいものを造ってほしい。 図書館や書店に行くと、読まれている本でその街の文化がわかる。小諸にはもっといい街になってほしい。100年語り継がれるようにという意気込みでつくってほしい。 利用していない人の目が覚めるような、利用したくなるものを造ればいい。 お金の掛け方が大事。人を育てるものにお金をかけてほしい。そのためにお金をかけるのはかまわない。 |
| 市民からの意見・要望 | 建設室・図書館からの回答 |
|---|---|
| どこまで決まっているのか?仮設図書館も決まっているのか? | 建設室:仮設については第1回目の懇談会から検討がはじまった。第1・2回を通して意見をいただいた。これから教育委員会としての方向性を出すところ。現図書館は、新市庁舎のプロポーザルのエリアに入っているし、スケジュールにも9~11月解体予定となっている。 |
| 新しい図書館からは緑が見えてほしい。まちなか多目的施設の位置はずらせないのか?あいおい公園が見えるように図書館と隣接させれば良いのでは? |
建設室:施設の位置を変更することは難しいと思う。まちなか多目的施設は市の施設ではない。 敷地の中での配置は、すでにプロポーザルでの提案に委ねられている。プロポーザルの第2回審査は公開なので見に来てほしい。 |
| 誰が選ぶのか? | 建設室:選考委員のみなさんが選ぶ。 |
|
市民も選考委員になれるのか? こちらの要望を伝えることはできるのか? |
建設室:選考委員はすでに決まっている。詳しくはホームページに公告が公開されているので、そちらを見てほしい。 まずはプロポーザルの提案を見て、図書館の併設が可能かの判断になる。市として併設が良いとの判断になれば、設計が始まるときに要望を伝えていく。ワークショップもあるようなので参加してほしい。 |
|
プロポーザルが心配。建物ばかり先行して、図書館というものをどれだけ配慮してもらえるのか? 公告のなかには、これまで懇談会でまとめた図書館のことを、よく盛り込んでいただいてあったとは思う。 |
建設室:こちらも連携して、これまで積み重ねてきたワークショップの意見が反映されるよう努力していく。 |
| いつ仮設へ引越しするのか? |
建設室:仮設をどうするかが決まっていないし、予算のこともあるので、議会にかける必要がある。まずは教育委員会で方向性を出していかなければならない。 面積・貸出冊数等どれくらいあれば図書館として営業できるのか、図書館と検討している段階。我々は、利用者優先、とくに中高生のための学習スペースや児童室を確保したいと考えており、図書館職員には申し訳ないが、作業スペースやストックスペースを別の場所、例えば既存施設などに持っていけないか相談している。また、職員の居るスペースも削り始めた。 図書館:気持ちよく使ってもらうためには、職員が気持ちよく働かないと良いサービスは提供できないと考えている。それには居場所が必要であり、作業スペースも出来るだけ一か所に全てあった方が効率的で職員の負担も減ると考える。 |
| できるだけお金をかけないようにしないと認められないのではないか?閲覧と作業場所と最低2つにわけて営業してはどうか?民間なら2年間だから我慢してほしいと職員に言う。最悪は閉館だが、職員の皆さんには悪いけど、縮小してでも続けてほしい。 | 建設室:費用については、税金を使うことなので、費用対効果に十分配慮したいと考えている。利用者には不便をかけ、職員にも負担をかけると思うが、承知していただきたい。 |
| 作業する場所、貸出する場所等2つに分かれる事のたいへんさはなにか? |
図書館:まず、そこに行くまでの選別作業がたいへん。 分散するとその分の人員も必要になってくる。出来る限り分散はしたくないと考えている。 |
| ボランティアに出来る作業はないのか? | 図書館:頼める部分は力仕事だと思う。そこまでに保存の本・廃棄本・貸出の本を選別する作業に時間がかかる。又、それをそれぞれの行き先に分ける必要がある。 |
|
仮設を設置しないで、例えば2年間とかの閉館になると厳しいが、マイナスにだけとらえず、人を育成する期間と考えることもできる。 面積に限界がある中では、すべて1か所にというのではなく、分割案も一理あると思う。仮設にお金をかけすぎて新図書館の時に抑えられては、おかしな話になってしまう。図書館は人が第1、資料・情報は第2で、建物は第3。今は建物が先行しがち。抑えられるところは抑えてほしい。 |
図書館:実際に高校生のころ、図書館が閉館していて利用できなかった。そのためかその地元の図書館に思い入れも親しみもない。高校生の時に接しておけばよかった本にその時接してこれなかったのは今考えれば、もったいないことだと思う。学生にとってはマイナスになる。閉館は考えていない。 作業スペースというが、机の上の作業ばかりではない。作業と一言でいっても様々な作業がある。新図書館に行く際には、きちんとした状態で開館したい。そのために必要な作業。ボランティアにもお願いしたいが、司書がやらなければならない作業も多いのが現状。 |
| 建設室:出来る事なら、仮設でも営業は続けていきたいと考えている。個人的な考えではあるが、中高生にとっての1年間は、私たちの1年間とは意味の違う大きな1年間。仮設であっても学習スペースは確保して、できるだけたくさんの中高生に利用してもらいたいと考えている。その利用が新図書館にもつながっていくと考える。 |
チラチラと雪の舞う寒い日でしたが、たくさんの方に参加いただきました。
ありがとうございました。
今回で市民懇談会は最終回となりましたが、図書館はこれからも市の施設として、市民のみなさんや利用者のみなさんと一緒に歩んでいきたいと思っていますので、よろしくお願いします。

昼の部には市民13名夜の部には市民9名の参加がありました。
今回の市民懇談会3回(昼の部・夜の部)で、計79名の方に参加いただき、貴重なご意見を聴かせていただきました。
「図書館の可能性は人間の可能性であり、また、図書館建築の可能性は、創造的な人間を成長させる空間の可能性でもある。」
大串夏身著 『触発する図書館』プロローグより
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市立小諸図書館
〒384-0025
長野県小諸市相生町3丁目3番3号 こもろプラザ内1階
電話:0267-22-1019 ファックス:0267-22-1165
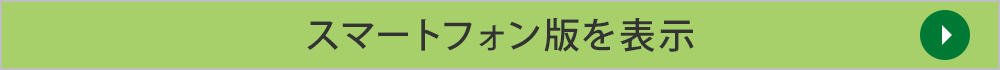
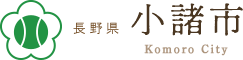
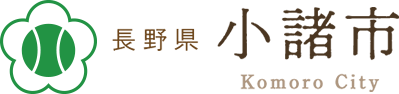

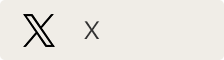


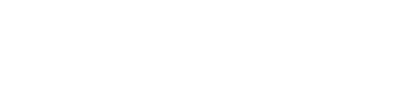

更新日:2021年03月28日